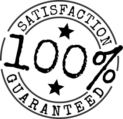【P1寺廻氏に聞く。プログラマティック・トレンドワードのいま】~第1回プライベートマーケットプレイス~

昨今サプライサイドで注目を集める「ヘッダービディング・S2S(Server to Server)接続」や「PMP(プライベート・マーケットプレイス)」、「アドベリフィケーション」。これらのキーワードについて、実務領域ではどのような現状にあるのか。
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の連結子会社で、プログラマティック領域の実務を担っている株式会社プラットフォーム・ワンの取締役副社長 寺廻友子氏にお話を伺った。
(聞き手:ExchangeWire Japan 野下 智之)
― PMPとはどのようなものでしょうか。
 一般的には取引に参加できるバイヤーとメディアが限定された取引をPMPとされているかと思います。
一般的には取引に参加できるバイヤーとメディアが限定された取引をPMPとされているかと思います。
RTBが普及し始めた頃、当初は「人」(オーディエンス)が重視されていました。その後プログラマティックの普及とともに、「人」と、「広告枠」または「掲載面」の両方を担保して、より幅の広い取引をプログラマティックで行うことを目的として生まれたのがPMPであると私は理解しています。
― PMPの普及背景についてお聞かせください。
従来のRTBによるオープンオークションの取引では扱いにくいクリエイティブが日本においてもプログラマティックで運用されはじめています。
例えば動画などのリッチなクリエイティブ、広告枠のスペースが大きいビルボード、スキンクリエイティブなどです。これらのクリエイティブがブランディング目的で使用されることが徐々に増えてきています。DSPで配信・レポーティングを一元管理したいという広告主様、広告会社様との間でも、これらのクリエイティブをRTB、プログラマティックで配信を出来ないのかという話が始まっており、それに対してPMPで対応できるということで、注目が集まりはじめました。
もう一点はビューアビリティをはじめとする、広告取引の透明性がプログマティックの世界でも重視されてきているということも、その解決策の一つとなり得るPMPが注目される背景にあります。
P1ではもともと存在していたPMP
― 貴社がPMPの提供を始めたのは、いつ頃ですか?
不思議な話で、2011年に当社を設立した際に、当社のDSP「MarketOne®」には、SSP「YIELD ONE®」の広告枠を指定して買い付けする機能と「YIELD ONE®」の広告枠を特定の「MarketOne®」利用広告主にのみ買い付けを許可する機能を付けていました。
この頃はまだPMPという言葉も浸透しておらず、当時私たちはプレイスメント・ターゲティングと呼んでいたのですが、後にPMPという言葉が普及し始めたとき、「あれ?これって、今まで私たちがやっていたことだよね?」となったタイミングがありました。
DACはメディアレップとして純広告の取り扱いをしており、その文化を継承したDSPとSSPであるからこそ、今でいうPMPの機能をもともと兼ね備えていました。当時は時期尚早だったのですが。(笑)
― その機能を使った取引は、当時の貴社のRTB取引で使われていましたか?
ほとんど使われていなかったという記憶があります。
当時は、RTBの利用はオーディエンスデータを何かしら掛け合わせて、リーチというか、掲載面は気にせずこのオーディエンスを捕まえたいというニーズに対するアプローチが圧倒的に多かったです。そのためにDSPに予算を割り振る時代だったので、ターゲットを絞ると配信量が落ちてしまい、この頃は「むしろなるべく使わないように。」というような社内の雰囲気がありました。
― その状況が変わったのはいつ頃ですか?
今から3、4年前からです。当社の場合は独自のプレイスメント・ターゲティングをOpenRTBベースのdeal idでの取引に変更したり、PMP専用の取引管理コンソール「XmediaOne PMP」の開発を行ったりしました。
従来のプログラマティック取引の課題解決が普及の背景
― PMPは、広告主とパブリッシャーとにそれぞれどのようなメリットがあるのでしょうか

広告主様にとっては、今までプログラマティック取引の課題とされてきた、広告の掲載先がどこであるかわからないというようなことを解消することができるようになります。ある程度DSPで広告枠や掲載時期、ターゲティングを管理しながら配信をすることが可能になります。広告配信の一元管理、配信先のコントロール、もしくはオーディエンスデータを掛け合わせた形で色々な媒体に一括で広告配信をすることができるということは大きなメリットです。
そして、DSPで一元管理することにより、媒体横断的なKPI・指標管理が行えるので、それをもとに判断したうえで、次の広告出稿に活かすことが可能になるため、プランニングのディシジョンがしやすくなります。
媒体社様のメリットは、プログラマティックの取引においても媒体価値が正当に判断される機会が増えるということです。今まではDSP側のロジックによる入札がすべてだったので、価格決定の基準は「DSP(広告主)がその時欲しいと思ったオーディエンスかどうか、パフォーマンスはどうか」といった感じで、どのような媒体であろうが変わらないということになりがちでした。
当社がお取引させていただいているプレミアムな媒体社様では、プログラマティックの世界においても媒体価値が正しく判断され、自分達のコンテンツや媒体価値が、広告単価に影響するというような世界観になっていくと思います。
ブランディング案件の取引に強みを発揮するチャネル
― PMPの強みを生かしやすいのは、どのような広告取引案件でしょうか?
ブランディング出稿の案件が挙げられます。ブランディングであれば当然どのような掲載面、どういった広告枠にどういった形で掲載されるのかを含めた「ブランドのイメージ」を追求する必要があると思うので、PMPとはとても親和性が高いです。
また、例えば「"自動車"などの、特定領域の専門性が高い媒体に掲載したい。」、もしくは「車の記事のページに出したい」というような話があった時に「そこをその期間、ある程度単価を上げて、量もある程度担保するので優先的に買いたい」といったニーズが出てきます。単純な単価勝負ではなく、広告会社様、DSPと当社のようなプラットフォーマーなどが介在して、媒体社様との関係性の中で、従来のプログラマティック取引から、純広告の取引に近いようなものへと幅が広がってきていると感じます。
― PMPに活かしやすいフォーマットはありますか。動画とリッチメディアでしょうか。
現在当社ではPMP取引の5〜6割が動画やリッチメディアを用いた取引になっています。広告主様側は、動画広告やリッチメディアを配信するとなると、インパクトの大きさから広告の掲載先はどこであるかということを気にされることが多くなります。また、リッチメディアフォーマットに関しては、通常のオープンオークションでは対応していないという媒体社様は数多くあります。そうなると必然的にPMPという取引形態が選択されることになります。
PMPを活かすコツは、しっかりと効果を返すこと
― 媒体社は、PMPと他のチャネル(純広告、OpenRTB、アドネットワークなど)と、どのように使い分けをすればよいのでしょうか。

究極的には、ヘッダービディングやS2Sの世界観の中で媒体社様の全てのリクエストにおいて、最適な販売チャネルを自動で呼び出せること、最適な値付けがされることがベストです。しかしそこに至るまでには、まだまだ時間がかかるでしょう。そして、バイヤーサイドにチャネルや単価に見合った効果を返せるようにする必要があります。例えば、PMPで純広に近い単価でオーダーが入れば、純広と同じプライオリティで、ファーストルックの在庫をしっかりと出す必要があります。そうでないと、そこのパフォーマンスの差で次からプランに入らないというような話にもなりかねません。
作業工数の短縮化が課題
― PMPの課題が何かあればお聞かせください。
現状は、PMPで取引をするために対応する工数が想定より大きい点が課題かなと思っています。プログラマティックといえど、まだ取引の全てが自動化されているわけではなく、案件取引に関する詳細なやり取りや、掲載確認、予算消化確認などを人が行う必要があるというのが現状です。この管理工数をどこまで自動化できるのだろうかということは課題に感じています。どうしても人手が介在することが多少は残るとは思うのですが、効率化へのアプローチはずっと続けていかなくてはいけないと思います。
ABOUT 野下 智之
ExchangeWire Japan 編集長
慶応義塾大学経済学部卒。
外資系消費財メーカーを経て、2006年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。
国内外のインターネット広告業界をはじめとするデジタル領域の市場・サービスの調査研究を担当し、関連する調査レポートを多数企画・発刊。
2016年4月にデジタル領域を対象とする市場・サービス評価をおこなう調査会社 株式会社デジタルインファクトを設立。
2021年1月に、行政DXをテーマにしたWeb情報媒体「デジタル行政」の立ち上げをリード。