ExchangeWire-ザ・談会 ストリーミング広告の今とこれから-
志(こころざし) 越えてつながる 春の波 ストリーミング広告(=インストリーム動画広告)の需要は、かつてないほどの高まりを見せている。 コネクテッドテレビの普及により存在感がますます高まる中、広告主にとって、ストリーミング広告はどのような位置づけになりつつあるのか。またプログラマティック取引により、今後ストリーミング広告でどのようなことが実現できるのか。 ストリーミング広告の今とこれからについて、お話を伺った。 福原 夕佳氏 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ メディアビジネス本部 パフォーマンスデザイン局 局長 土屋 尚氏 株式会社フジテレビジョン 技術局 デジタルメディア技術部 担当部長 広告配信サーバー管理 香川 晴代氏 Index Exchange Japan株式会社 日本担当 マネージングディレクター -皆さまのビジネスにおけるインストリーム広告との関わりについて、お聞かせください。 土屋氏:フジテレビの技術局(営業局にも兼務中)で、TVerとFODのインストリーム広告枠の管理をしています。広告サーバーの管理業務や広告在庫をどのような配分でどのような取引形式で売っていこうかという販売戦略の策定を行っています。 福原氏:メディアビジネス本部に所属し、広告主であるクライアントに対して、デジタルメディアの運用戦略から実行までをコンサルティングしています。ストリーミング広告においては日々Googleをはじめとするプラットフォーマー各社と連携しながら、YouTubeや運用型広告のTVerなどのプランニングをしております。 香川氏:グローバルのアドエクスチェンジ事業者として、ストリーミング広告の技術開発に関わっています。ストリーミング広告とは切り離すことが出来ないコネクテッドテレビ領域への注力をしています。2024年の米国のコネクテッドテレビ広告市場は前年比21.7%増、約287億ドルと、巨大な規模に達しています。 日本の市場に関しては、私たちは海外で蓄積した色々な知見、ベストプラクティスを提供していこうとしています。業界の啓蒙活動の一環として、「Index Explains」という動画シリーズを通じて、ストリーミングTVの動画広告について分かりやすい解説を共有しています。 -ストリーミング広告の市場シェアは圧倒的にYouTubeが持っており、そこにTVerやABEMAが追随する構造になっています。福原さんに伺いたいのですが、広告主は各媒体にどのような意識でストリーミング広告を出稿しているのでしょうか。 福原氏:YouTubeは国内で最も多くのユーザーを抱える動画プラットフォームであり、幅広い層へのリーチを目指す広告主にとって最重要の選択肢とされています。 一方で、TVerやABEMAはエージェンシーのプランニングツールを用いてリーチ効率を比較すると、YouTubeに劣る傾向があります。そのため、これらの媒体はリーチ効率よりもコンテンツの質を重視するプランニングにおいて選択されることが多いと考えられます。 これらの媒体とYouTubeの大きな違いは、ユーザーの視聴態度にあるのではないでしょうか。YouTubeには、従来のテレビ視聴のように、目的を持たずに動画を視聴する傾向が見られる一方、TVerやABEMAは特定のコンテンツを目的として視聴されるため、ユーザーのエンゲージメントが高いと考えられます。広告主は、このような視聴態度の違いを考慮し、広範なリーチを目的とする場合はYouTubeを、コンテンツとの関連性を重視した広告出稿を行いたい場合はTVerやABEMAを、といったように使い分けているのではないでしょうか。 -TVerやFODにストリーミング広告を出稿する広告主は、どのような意識をもってしているとお考えでしょうか? 土屋氏:おかげさまでTVerやFODの売上規模もどんどん成長してきています。新規のお客様も非常に増えています。広告主の皆さまに認知頂いており、プランニングにも含めていただいていることが増えていると実感しています。 ブランドセーフティの意識の高まりと共に、TVerであればテレビと同じコンテンツに出稿するということですので、出稿先への不安はないということについて、直接広告主の方からもお声をいただくこともあります。 -日本の広告主と海外の広告主と比較した時、何か意識の違いについてお気づきの点はありますか? 香川氏:海外ではプログラマティックの技術導入が進んでいます。テクノロジーを活用して、テレビのストリーミング広告を出稿していくということを、海外の広告主は積極的にやっています。特にテレビに広く出稿することが自由にできない中小広告主であっても、プログラマティックであれば、特定領域に集中して投資をすることが可能です。可能な予算範囲でターゲティングニーズにかなう範囲での手法として広がってきています。また、グローバルでは、広告主、放送局をはじめとする媒体社の双方がプログラマティックの導入を加速させています。 一方で、日本はまだこれからであるという認識をしています。 福原氏:TVerをプログラマティックで買い付けする場合には、第三者のデータを使うことが出来ますので、TVerでターゲティングをすることについては根付いてきているのかなと思います。 -TVer側でも、ターゲティングが出来る環境を進めているのでしょうか? 土屋氏:そうですね。ターゲティングは大きく二つあります。一つはオーディエンスターゲティングです。そして、もう一つはコンテンツターゲティングですが、この領域で新しい取り組みとして進めているものがあります。我々はコンテンツ情報を一次情報として保有しており、コンテンツ情報を開放していくというものです。例えば、コンテンツのジャンル、サブジャンルのようなものから、最終的には演者の情報などもです。あるいは、そのコンテンツにどのようなシーンがあるのかなどの情報を付与する事でコンテキストターゲティングも可能にななります。コンテンツの中身に関する情報をしっかりと整理していって、これを使って広告枠の買い付けを行って頂ける様な取り組みを進めています。 背景として、純広告で我々が「演者マッチング」と言っているメニューが非常に人気な事があります。これは、CMに出演している演者が主演、助演をしているドラマコンテンツへコンテンツターゲティングする事により広告のパフォーマンスを上げる事ができる物です。視聴者は該当の演者をチェックしてドラマを視聴しており、当然その広告も忌避感なくしっかりと見て頂けます。このようなものは、UGCでは難しい取り組みであり、差別化という意味で我々としても力を入れているところです。 普及するコネクテッドテレビが変える、ストリーミング広告の出稿環境 ―コネクテッドテレビは今日本でも普及が進んでいますが、広告の量はどのくらい増えているのでしょうか。 土屋氏:今TVerでは、本篇の再生数ベースですと約3割がコネクテッドテレビ経由で視聴されています。一方、広告配信サーバー側から在庫量ベースでみると、既に全体の4割を超えていますし、今後も増え続けるでしょう。これはスマホやPCなどよりもコネクテッドテレビ視聴のほうが、より長く視聴されますので、本篇1再生当たりの広告在庫ボリュームは多くなる事が起因しています。 -広告主側は、配信先をコネクテッドテレビに指定をして出稿をするようになっていますか? 福原氏:基本的にどの広告主もコネクテッドテレビを含めて配信しています。当社が実施した配信結果を調べてみても、YouTubeの場合には今はデバイスを指定しなくとも、4割を超える割合でコネクテッドテレビに配信されています。 コネクテッドテレビに限定するかどうかは、キャンペーンの設計によって異なると考えられます。 デバイスをコネクテッドテレビに限定することは、リーチやコンバージョンなどの機会損失につながるため、あえてデバイスを絞り込むメリットは少ないと言えるでしょう。 テレビCMと同じ役割でストリーミング広告を活用する場合は、画面占有率の高いコネクテッドテレビに限定してYouTubeやTVerへの出稿をする広告主も一定はいらっしゃいます。 -効果測定は今どのようにしているのでしょうか? 福原氏:デジタル中心のキャンペーンにおいては、従来のスマートフォンやPCといったデバイスと比較して、コネクテッドテレビがもたらす効果の大きさに改めて注目しています。特に、その高い画面占有率が、広告の視認性や記憶への定着に大きく貢献していることが、弊社の比較調査からも明らかになっています。 近年では、テレビCMと比較評価したいという広告主のニーズが顕著になってきており、 当社でもREVISIOを活用して注視率を計測することが増えています。 コネクテッドテレビの場合は、このコンテンツを見に行くという意識でユーザーが視聴するため、テレビCMよりも注視率は高いという弊社の調査結果も出ています。 土屋氏:コネクテッドテレビはスマートデバイスとは環境が異なり、クリックスルー等の直接的なコンバージョンを得ることが出来ないデバイスです。パフォーマンスのレポートについては、Adjust、AppsFlyerのようなパートナーとの連携など、対応を進めています。 -欧米ではどのような状況なのでしょうか? 香川氏:コネクテッドテレビにおける計測の標準化はまだ出来ていません。どこの会社の手法をメインとするかについては、様々な議論が続いています。大手の計測会社が提供するサービスもあれば、複数の大手メディア企業が一緒になって提供をしている計測サービスもあります。 先ほど福原さんがおっしゃったように、テレビCMからの広告主と、デジタル広告からの広告主とでは計測に対するニーズも異なっています。 それぞれに応じたサービスを提供するベンダーが存在するという状況です。 広告主がリーチしたい人に、より透明性を持ってリーチするのかということについては、私たちは媒体と直接つながっている立場として、出来るだけたくさんの情報をバイサイドに届けるよう努めています。ログレベルでのデータを提供しているため、いつどのような広告枠を購入しているかを正確に把握できます。 また、色々なデータを活用して、広告効果を測定をしていくような取り組みも行っています。 例えば、ターゲティングをして、当てたい人に当たっているのかどうかを測る目的で、媒体社から様々なシグナルを受け取る技術を採用していますし、これが精度の高い計測につながっています。例えば、番組のコンテンツジャンルやレーティング、ライブストリームの有無、言語、番組名、シーズン数、放送回タイトルなどの番組単位の情報がこれに含まれます。 ストリーミング広告の今後と、プログラマティックの可能性 ―ストリーミング広告は媒体の選択肢が限られていたことが、課題にもなっています。 福原氏:状況は変わりつつあります。AmazonPrimeVideoでのインストリーム広告の提供が、欧米で始まりました。日本においてもこの4月からプライム会員を対象に広告表示がスタートしました。 香川氏:その他にも、NTTドコモのLeminoや楽天のRチャンネル、グローバル企業のパラマウントとWOWOWとが提携をして、日本でParamount+の提供を開始しましたね。このように、選択肢は増えつつあります。地上波広告のプログラマティック取引が日本テレビでこの春からスタートするのは目覚ましい動きとして注目されています。 福原氏:FAST(Free Ad-supported Streaming Television)のビジネスモデルを社名に冠した「FASTチャンネル」社は、昨年サービスを開始しました。 土屋氏:FASTに関しては、日本でサービスを拡大していくうえで、日本固有の参入障壁が存在するのではないかと考えています。 欧米でFASTが盛り上がりを見せた背景には、無料で視聴可能な形で、過去に制作された人気コンテンツを再活用し、ユーザーがCTV上でザッピングしながら気軽に楽しめる環境が、それまで存在していなかったという点があります。 さらに、新型コロナウイルスの影響により家庭内での可処分時間が増加したこと、そしてインフレの影響によってユーザーが新たなサブスクリプションサービスへの加入を避ける傾向が強まったことも、FASTの成長を後押しした大きな要因であると考えております。 ですが日本にはもともと無料で気軽に楽しめる地上波テレビがあり、そのジャンルのカバー範囲は広く、コンテンツはまだまだ強いです。供給力をみても、新たに日本オリジナルでチャンネルサービスを開始し一定のレベルを維持するということは、容易ではありません。絶えず一定レベルの新作コンテンツを作り続ける体力があるコンテンツ事業者はなかなかいませんし、欧米の様に過去作を上手く使おうと思って複雑な著作権処理をしっかりと行った上で大量にコンテンツを揃える事は日本の環境では難しく思います。 更に収益性の観点で見ても、日本では、今のところUGCと言われているメディアと、プロコンテンツのメディアとがはっきりと差別化されていません。我々は定性的な説明だけでなく定量的にパフォーマンスに差がある事を証明し続けなければいけないと思います。 香川氏:UGCとプロコンテンツに、相応の対価を払い分けるということは海外では一般的なことです。プロフェッショナルコンテンツと、UGCと同じCPMで諮るということはしません。私がこの話を海外の同僚にすると、「質の異なるコンテンツに対して、それぞれ相応の対価を払うのは当たり前のことであり、なぜそのようなことが議論になるのかわからない。」と言われます。 福原氏:これは日本のデジタル広告市場における特有の課題、あるいは私たち広告会社が向き合うべき課題なのかもしれませんが、「1インプレッション単価の価値」に対する議論が深まらない現状があります。YouTubeであろうとTVerであろうと、一律の価値として捉えられ、プランニングが進められているケースが散見されます。背景には、日本の広告主の、ある意味で徹底したパフォーマンス重視の姿勢があると考えられます。「より安価に、より広範囲にリーチできること」が、依然として重要な指標として捉えられているのではないでしょうか。 この点は外資系の広告主は、例えばブランドセーフティの観点からUGCには出稿しないといった、厳密なルールを設定するケースもあり、コンテンツに対するこだわりを持っていらっしゃいます。 土屋氏:地上波テレビとYouTubeのクロスメディアプランニングは1つのパターンになっていますが、 地上波テレビとYouTubeとでは、コンテンツや視聴体験の同質性がない中で、福原さんが仰っている通り可能な限り安価にリーチを補完するというというものです。 今はTVerも広告在庫が増加してきておりますし、広告主の方にプレミアムなAVOD広告枠の価値を評価頂ける様に努めています。 ―放送局がTVCMをプログラマティックでバイイング出来るサービスを開始しましたが、今後TVCMでもプログラマティックバイイングが主流になるのでしょうか? 土屋氏:広告枠が有限、固定的である以上、主流になるとは言えませんが一部の広告枠をデジタル化していくという動きはあると思います。先ほどテレビでターゲティングをするという話がありましたが、欧米ではアドレッサブルと呼ばれる、地上波テレビ広告枠をターゲティング可能にする技術が出来てきています。 本篇の再生は地上波受信によるものですが、インターネット結線されているテレビに対して、広告はインターネット経由で配信されるという物です。 アドレッサブルというのは、まさにこの切り替えをスムーズにして、ターゲティングをすることが出来るという技術です。これについては、徐々にフィージビリティが高まってきておりプログラマティックバイイングを後押しする要因になり得ると思います。 ―現状は寡占化されている日本において、媒体社が広告在庫をオープン化して、プログラマティックで買い付けが出来るようにするインセンティブはどこにあるのでしょうか? 土屋氏:広告業界におけるオープン化というのは聞こえは良いのですが、一方でクリエイティブや視聴体験の悪化に繋がる様な印象が媒体としてはあります。我々はオープンであっても事前にクリエイティブの審査をする必要性があると感じています。この作業はAIの進化によって、かなりスピーディーになり事後審査によるベストエフォートな物と事前審査とのタイムラグを中長期的には改善してくれると期待しています。 これまで、オープンな環境で事後考査もしくは事前審査はしていると言っているが明らかにその精度について疑わしい仕組みが広がったことで、劣悪な体験が増えてしまったのでしょう。そういった環境へそのまま我々がでていくことはないでしょう。 一方で、広告枠のデジタル化というのは広告枠の特性が多様化し枠数も爆発的に増えるという事です。そう考えると中小規模でも、業態やクリエイティブの考査、出稿単価に問題がなければ、我々としては出稿頂きたいと当然考えます。広告主としてもプレミアムな媒体に簡単にアクセスできる事は良いことだとお思います。そうなると結果としてオープンでプログラマティックというのは我々の広告枠を埋めてくれて広告主にもその価値を与えてくれる物になると思います。そういった意味では、オープンだクローズドだという事にあまり囚われるのは良くないのではないかと思います。 香川氏:デジタルの世界では、ディスプレイ広告とストリーミング広告では、フォーマットが異なりますが、ディスプレイ広告において、最初は予約型広告のみで、その後プログラマティック化し、プログラマティックが中心になったように、ストリーミング広告もプログラマティックが主流になっていく点には議論の余地はないと思っています。 メリットは、媒体社からすると圧倒的な数の広告主からの出稿を受けられることや、取引の簡便化などが挙げられます。プログラマティック取引は、標準化された自動入札の取引ですので、マニュアル作業は大幅に軽減されます。将来は、より簡略化された最適な取引として発展していく可能性もあります。 ―プログラマティックに対する期待する点はありますか? 福原氏:香川さんがおっしゃったように、デジタルの良いところを取り入れて、まずは発展していけるのはとてもいいことかなと思います。 香川氏:意外な話かもしれませんが、テレビCMで当たり前にできていることが、逆にコネクテッドテレビではできていなかった、そんなこともあります。テレビCMでは、1つの番組で複数の広告主が入りますが、同業種の競合企業の広告が並ぶことはありません。例えばトヨタ、ホンダ、スズキのCMが連続して出ることはありませんよね。 コネクテッドテレビでは、当初これが出来なかったのですが、技術が確立してできるようになりました。 具体的には、OpenRTB2.6というプロトコルのお陰です。当社では、OpenRTB2.6をIABTechLabと一緒に作ってきました。このプロトコルに含まれる広告Podという技術により、テレビの視聴者や広告主が当たり前と感じている視聴体験をコネクテッドテレビでも実現することが出来るようになりました。 もう一つ海外で今注目を集めているのが、ライブストリーミングです。ライブストリーミングは、どのタイミングでどのくらいのユーザーが見に来るのかが予測できないものです。 視聴者の注目を集める試合のピーク時に、広告出稿の大チャンスが訪れます。 視聴者数が集中した時の大規模な自動広告取引に耐えうる技術的なインフラの開発に、世界の注目が集まっています。当社は業界標準を構築し、これを現実のものとするために貢献していきます。 土屋氏:ライブスポーツは、一部の伝統的で非常に人気なものを除くとインプレッション数の予測が難しく、純広告として枠を販売していくのが難しかったのです。 これをプログラマティックで販売できるようになると、マネタイズがしやすくなることが期待されます。 また、コネクテッドテレビ画面は大きいので、Lバンドや、サイド・バイ・サイドと呼ばれるような、画面にコンテンツと広告が一緒に流れるようなフォーマットの提供がしやすくなります。例えば、一般的にCMが入れにくいと言われているサッカーの試合でも、ゴールが決まったとき、挿入するなどの取り組みが出来るようになります。 そういった意味でも、コネクテッドテレビとプログラマティックで、ライブスポーツのマネタイズの可能性が広がります。 香川氏:国内でもストリーミング広告のプログラマティック取引は着実に伸びていきます。グローバル市場で事業を手掛ける当社としては、欧米市場のベストプラクティスと技術を提供し、国内市場の発展を支える役割を、引き続き担っていきたいと思います。
130周年を迎える東洋経済が『変えること』と『変えないこと』―東洋経済新報社×FLUX対談
創立130周年を迎える東洋経済新報社。「社会を良くする経済ニュース」の配信を行う東洋経済オンラインは経済・ビジネスに特化したメディアとして、確固たる地位を築いている。伝統ある経済紙としてのこだわりと、めまぐるしく変化するメディア環境の中での新しい挑戦について、メディア支援を担うFLUXが話を伺った。本対談は2025年2月 東洋経済新報社本社にて行われた。 (Sponsored by FLUX) 堀越 千代 東洋経済新報社 執行役員 東洋経済オンラインプロデューサー 2006年東洋経済新報社に⼊社。業界記者として⼩売り、化学、外⾷業界などを担当。雑誌『週刊東洋経済』編集部、新規媒体開発担当などを経た後、2017年に編集局を離れ、デジタルマーケティングの領域へ。会員制サイトのプロダクトマネジャー、東洋経済ID施策担当などを担う。2023年4⽉、東洋経済オンライン事業局長、2025年3月から現職。 柳田 竜哉 株式会社FLUX VP of Publisher メディア・マーケティングソリューション本部長 2001年朝日新聞社入社。広告局、デジタルメディア本部を経て2010年より朝日インタラクティブ社に出向。CNET japan・CNN.co.jp等を取締役として統括。2016年に朝日新聞社に帰任し、アドテク・運用型広告の領域に注力。2020年4月にFLUXに参画。 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社が運営する「社会を良くする経済ニュース」を配信する情報配信プラットフォーム。毎⽉約1,000本の記事を公開し、⽉間PVは1億を超える。100人を超える社内記者に加え、様々な分野の有識者といった外部著者のべ400人が、一つの事象に対してあらゆる視点での分析を試み、日々記事を生み出している。 東洋経済オンライン22年の歩みと成長の軌跡 堀越:東洋経済オンラインは2003年にローンチし、今年で22年目となります。今の形にリニューアルしたのが2012年です。社内記者に加えて社外有識者の方々にも記事を書いていただくという体制を確立し、ウェブメディア業界全体の勃興とともに急成長してきました。特にコロナ禍でメディアの需要が急増し、2020年には月間で3億PVを超えるまでに至りました。 ユーザーの拡大とともに広告市場の追い風を受け、業績も右肩上がりで推移してきました。 コンテンツ視点とビジネス視点の融合が求められるフェーズ 柳田:堀越さんは2006年に東洋経済に入社後、記者・編集・新媒体の開発やマーケティングを経て、2023年に東洋経済オンライン事業部が新設されると同時に、事業全体つまり経営面の役職に就かれていますが、東洋経済さんでは編集出身者がビジネス(メディアの経営)を担うのはよくあることですか? 堀越:珍しい方かもしれません。今後も理想としては、コンテンツ制作とビジネスの両方がわかる人を増やしていきたいと考えています。 柳田:コンテンツとビジネスの両方のことがわかる人がメディアの中にもっといるといいなと思います。ベンチャー系のメディアだと、皆が全てに関わるためスピード感が早いなと感じることがありますが、大規模な伝統ある企業ではコンテンツ制作とビジネス視点が分断されがちです。今は、そういった点でも変化が求められる局面にあるのかもしれません。 激変するメディア環境、立ち止まる2024年 柳田:昨今メディア環境が大きく変わってきていますが、現状の事業環境をどのように捉えられていますか。 堀越:インターネットメディアを取り巻く環境はネガティブなことが多いと感じます。以前は記事を出せばユーザーが集まり、広告も出稿されるというビジネスモデルが成り立っていました。しかし、ここ2〜3年でその状況は大きく変わり、「このままではいけない」と痛感しています。 最大の課題は、そもそもニュースサイトを訪れるユーザーが減っていることです。特定の話題で瞬間的にアクセスが増えることはありますが、全体的に見ると特にテキストコンテンツを読むユーザーが縮小していると感じます。 私たちはこの10年間、「よい記事さえ出せばユーザーが来る」状況に慣れてしまっていたのかもしれません。しかしながら、今後このままではいられないため、2024年は一度立ち止まり、会社として「これからのメディアの在り方」について本気で考え直す年にしました。 東洋経済オンラインの再定義と「ステートメント」 堀越:昨年、これまで明文化されていなかった東洋経済オンラインのミッションやビジョンを、「ステートメント」として定義しました。東洋経済新報社では、今から130年前『東洋経済新報』の創刊時に記された「健全なる経済社会に貢献する」という言葉を企業理念として、これまでも各業務にあたる社員それぞれが思いを持って、クライアントやユーザーに向き合ってきました。しかし、改めて事業に関わる人全体で認識を共有するために、言語化するための試みとしてステートメントを作成することにしたのです。 ステートメント策定に際し、定量・定性調査、今置かれている現状や課題のためにやるべきこと、未来に向かってやるべきことをさまざまな部門で考えました。また一度作成したものに対しても全社から意見を募集し、それを細かいところまで反映させました。こうして策定した東洋経済オンラインのミッションは「経済・ビジネスを軸に、あらゆる人々が『よりよい選択』をできるよう手助けし、豊かで健全な経済社会を実現すること」です。 これから新しい提案や取り組みをするとき際には、このミッションに基づいて意思決定をしていきたいと考えています。 「読まれる」だけでなく、「社会的意義のある記事」を 柳田:次に、御社のコンテンツ作りについてお伺いさせてください。先ほどインターネットメディアに訪れるユーザーが減っているというお話がありましたが、コンテンツ作りで課題に感じていることなどありますか? 堀越:コンテンツ作りにおいて、マーケットイン(読者のニーズを出発点としてコンテンツ作成を優先する)かプロダクトアウト(東洋経済が発信したいコンテンツを優先するか)か、これまでたくさん迷い、悩んできています。 記者に対して、ビジネス部門からマネタイズを意識するような枠にはめた指示を出せば、面白い記事が出なくなります。記者のクリエイティビティと熱量がないと良い記事は生まれないんです。 柳田:SNSを中心にインフルエンサーと呼ばれる個人による発信が「バズる」時代に、東洋経済オンラインのように専業記者が発信しているメディアの存在意義についてはどうお考えですか。 堀越:確かに、個人のインフルエンサーが影響力を持つ時代です。しかし一方で、東洋経済オンラインは「まとまり」で運営しているのが強みだと考えています。 個人インフルエンサーのマーケットイン的な発想では、「みんなが知りたいこと」を優先して発信すれば良いかもしれません。しかし、多くの人には読まれないかもしれないけれど「今、書かなければならない」という社会的意義がある記事を出せるのは、やはり東洋経済の強みであり、存在意義なのではないかと思います。 弊社は広く名が知れたスター記者がいるわけではありませんが、130年続いてきたメディアとしての責任と信頼があります。一部の人にしか読まれないかもしれないけれど、社会的に重要な記事を発信し続けることこそ、私たちの役割だと考えています。 柳田:まさに御社で発行されている会社四季報がそうですよね。メジャーな企業だけでは成立せず、どんなに小さな銘柄までも網羅していることが価値であると感じます。個人がメディアのようなこともできるというのは面白い時代でもありますが、「まとまり」の大切さには共感します。 FLUXも顧客であるメディアの皆様に対してSEO関連のサポートをすることがあります。やはり「読まれる記事を書く」というのは基本ではあるのですが、「たくさん読まれるだけの記事」では価値を生み出しにくい側面があります。ビジネスとコンテンツのバランスが重要ですね。 堀越:そのバランスを取るのが、まさに今の課題です。マネタイズを強化しすぎると、熱量のある記事が生まれにくくなる。一方で、取材記者は単なる情報発信者ではなく、クリエイターでもある。収益とジャーナリズムの両立をどう図るか、メディア運営において極めて重要なテーマだと思っています。 新たなチャレンジ、動画コンテンツへの再注力 柳田:最近はYouTube動画にも力を入れていますね。 堀越:そうですね。YouTubeチャンネルは以前からありましたが、2024年から本格的にリスタートしました。現在は月20本程度のペースで動画を配信しています。 YouTubeこそ「見られるもの」が「稼ぎ」となりますが、そこで東洋経済らしさをどう出すのかは懸念としてありました。しかし、テキストを読むユーザーが減少している中で、新しいユーザーとの接点を増やす意味でも動画配信には取り組むべきだと考え、YouTubeに再注力することにしました。 柳田:最近も、とある大企業の合併破談についての解説動画がありましたが、ニュースが出てすぐに動画で配信されていましたね。裏話も入っていてとても面白かったです。 堀越:動画における弊社の強みはスピード感です。記者はずっと最前線で取材をしているため、ニュースが出てすぐに記者が解説することができます。 また、動画のフォーマットも工夫しており、編集長が記者に質問を投げかけ、それに記者が答えるという形を取っています。これは、実は記事作成における編集部の日常的な風景をそのまま切り取ったものなんです。そこにも面白さを感じて頂きたいのですが、弊社としては簡単な打ち合わせをすればすぐに収録できる点も大きな利点ですし、動画には新しい可能性を感じています。 ファンとの関係を強化する取り組み 柳田:今新たに注力している領域はありますか。 堀越:東洋経済オンラインのファンを大事にするためにも、読者に対して然るべきサービスを提供することは今後より注力していきたいと考えています。 直近ではユーザー調査を実施し、「ロイヤルユーザー」の分類を再確認しました。そこには、有料会員と、無料ながら頻繁に訪問してくれるユーザーの両方が存在します。どちらも重要な読者層なので、それぞれに適した価値を提供することが必要だと考えています。その中でも特に有料会員であるユーザーには、より付加価値の高いサービスを提供していきたいという話を、ユーザー調査の結果を元に記者も含めて会社として再確認したところです。 柳田:こういったユーザー調査をすると、コンテンツを作る時にも意識するようになりますし、広告主に対して「こういったユーザーがメインとなるのでそういう広告を出してください」と言えるようにもなりますよね。 広告はきちんとターゲットが合えばとても有用な情報となりますし、IDを活用してユーザー属性を明確にすることで、マーケティング担当者から見ても非常に魅力的なメディアになるはずです。 収益化とコンテンツの質、マネタイズ戦略の多様化 柳田:FLUXでは大小様々なメディアの広告マネタイズをお手伝いさせていただいています。その中でも、東洋経済オンラインさんは、読者や広告主にとっての最適とは何かをしっかりと考えて運用なされている印象です。 堀越:ありがとうございます。運用型広告は、ユーザーと広告主の双方にとって最適な形を常に模索しています。 柳田:特に御社のようなプレミアムなメディアにおいては、ブランドセーフティの確保が広告主にとっても非常に重要ですよね。我々FLUXとしても、広告が適切なコンテンツの中で表示され、読者の信頼を損なわない環境を作ることを重要と考えています。 堀越:特に東洋経済オンラインのようなメディアでは、広告の質や掲載環境がブランドイメージにも直結します。ユーザーはもちろんですが、広告主の期待に応えられるよう、厳格な基準を設けています。 柳田:広告収益は一つの収益の柱であるかと思いますが、そのほかサブスクや記事提供も収入柱になっていますか? 堀越:はい、ただサブスクに関してはまだ発展途上です。というのも、有料読者のみが閲覧できるという、いわゆる記事に鍵をかけただけではサブスクは成立しないと思っています。今後はより一層、読者が「東洋経済の有料会員になりたい」と思える付加価値を提供しなければならないと考えています。 柳田:いい記事ほど鍵をかけたくない(有料読者のみが閲覧できる状況にしたくない)と仰っていたことがありましたがとても共感できました。記事ではないところの付加価値をつけるというのは面白いですね。 堀越:また、もう一つの収入柱である「記事提供」に関しては、記事を生成AIの学習用データとしての販売を始めました。これは単なる収益化というだけではなく、ある種の防衛策とも言えますが、無断利用されないために販売しているという側面もあります。販売先は生成AI事業者のみならず、企業が生成AIを活用する際のデータとしても利用されています。ビジネス領域に特化した日本語データかつ、図表を交えたコンテンツというのは希少であり、東洋経済オンラインの強みを活かすあまり他にはないデータなので有用性が高いと思います。 創立130周年に向けて、東洋経済の未来を語る 柳田:東洋経済新報社は今年11月に130周年を迎えられます。今までと変わらず大切にしていきたいことと、これからの展望をお聞かせいただけますか。 堀越:やはり弊社の強みであり中核は、経済・ビジネスのコンテンツです。この強みを活かしながら、今後も価値あるコンテンツを提供し続けることが重要だと考えています。 また、130周年事業の一環として、サイトのリニューアルも予定しています。実は前回のサイトリニューアルから10年以上が経過しており、これまで小規模な改修は繰り返してきましたが、今回は抜本的な見直しを行います。また、動画コンテンツやサブスクリプションといった新たな要素を本格的に取り入れることも検討しているので、楽しみにしていただければと思います。 柳田:業界全体が厳しい状況にある中で、積極的な投資と改革に取り組まれるのは素晴らしいですね。サイトリニューアルも含め、東洋経済の今後の取り組みをとても楽しみにしています。本日は貴重なお話をありがとうございました。
明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]―ATS Tokyo 2024イベントレポート
デジタルメディアとマーケティング業界の有識者が一堂に会し、業界の最新動向についての議論を行うイベント「ATS Tokyo 2024」が2024年11月22日、都内にて開催された。 ATS Tokyo 2024のトリを飾るセッションには、2年連続で高広 伯彦氏(社会構想大学院大学 コミュニケーション・デザイン研究科 特任教授)が登壇。 「明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]」と題したタイトルで、プレゼンテーションを行った。プレゼンテーション後のモデレーターはExchangeWire JAPAN 編集長 野下 智之が務めた。 この特徴的なタイトルは、高広氏が電通に勤務していた時の上司、佐藤尚之氏が執筆した「明日の広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法」(2008年/アスキー)をアレンジしたもの。なお、タイトルの利用については、佐藤氏に許可を得たうえでのことだそうだ。 本セッションでは、長年業界を見続けてきた同氏が、消費者にとって悪しきものになりつつあるインターネット広告の現状を、どうすれば良い方向へ導けるのか、という議題が改めて提起された。 20年以上にわたり広告、マーケティング、デジタル領域の企画開発・事業開発に携わってきた高広氏は、いくつかのキーワードを軸に、インターネット広告の歴史を振り返りながら、インターネット広告業界が抱える課題を紐解いた。 クッキーレス問題、ユーザビリティを犠牲にした過剰な広告表示、不快なクリエイティブ、不公平なアプリ広告の計測環境など、デジタル業界の課題は山積みだ。高広氏は、パブリッシャー側の問題、広告主側の問題、技術的な問題、エコシステムの問題の中で、現在最も深刻な問題はエコシステムの問題だと指摘。この問題の解決には、パブリッシャーや広告主だけでなく、業界全体での協力が不可欠だと述べた。そして、こうした問題の根本原因として、広告の歴史の軽視、過去の失敗からの学びの欠如を挙げた。 高広氏は、20年間アドテク業界を見てきた中で、まるでデジャヴのように、業界が同じ失敗をしているところを4~5回は見てきたという。 「過去の同様の失敗を、業界は忘れてしまっている。あるいは、現在の業界関係者は、過去にそのような問題があったことすら知らないのではないか」 と述べ、一度立ち止まり、歴史を振り返って考えることの重要性を訴えた。 また、重要でありながら忘れられている概念として「パーミッションマーケティング」を挙げた。「インタラプションマーケティング」(日本では「土足マーケティング」と訳された)の対義語として登場したパーミッションマーケティングは、顧客の許諾(パーミッション)を得て情報を提供するという考え方だ。当時主流だったメールマーケティングを基に生まれたこの考え方は、顧客ニーズを把握し、適切な情報を提供するというもので、現在のインバウンドマーケティングやインテントセールスなど、あらゆるマーケティング・セールス領域の核となる重要な概念と言える。しかし、業界はこの基本的な考え方を忘れ、新しいマーケティング手法にばかり目を向けていると指摘した。 さらに、クッキーとユーザー体験を阻害する広告についても言及。 「クッキーは本来、ユーザーが毎回ログインする手間を省くために用いられていた。しかし、今は違う。ユーザーのための技術だったことを忘れている。『誰のためのテクノロジーなのか?』という視点が業界に欠けている」 と指摘した。続けて 「インターネットが定額制ではなく、ダイアルアップ接続だった時代、ユーザーは接続時間に応じて料金を支払っていた。つまり、ユーザーは広告を見るためにお金を払っていたと言える。この時代に生まれた『広告は情報として有益でなければならない』という価値観は、インターネット黎明期に、メディア体験を阻害する広告を排除する動きにつながった。邪魔な広告を排除するという考え方は、20年以上前から存在していたにもかかわらず、再び邪魔な広告が問題となっている。これは、業界が過去の教訓を忘れてしまったからだ」 と述べた。 今広告業界に必要なのは イノベーションではなくリノベーション 高広氏はGoogle時代に、Google Print AdsやGoogle TV Ads(後にGoogle TVと改称)の開発に携わっていた。 Google Print Adsには、広告主のリクエストをパブリッシャーが価格の安さを理由に拒否できる「リジェクトオーバーカウンター」という仕組みがあった。これは単なる拒否機能ではなく、拒否回数の上限を設定することで、広告主とパブリッシャーの間の価格交渉を促す双方向のネゴシエーションを実現するためのものだった。 また、GoogleのテレビCM販売プラットフォーム「Google TV Ads」の開発にも携わっていた。Googleの検索連動型広告のような革新的な広告とは異なり、Google TV Adsは従来の広告ビジネスの仕組みを改善する、いわば「リノベーション」を目指していた。Googleアナリティクスとの連携によるテレビCM放映時のトラフィック増加などのデータ分析機能に加え、CM制作会社と広告主の連携機能、広告テキストからの自動広告生成機能なども開発していた。 高広氏によると、これらの取り組みの背景には、ジョン・ワナメーカーの有名な言葉「広告費の半分は無駄になっているが、どの半分かはわからない」に対するGoogleの危機感があったという。 「この状況を打破するために、Googleはシンプルな広告プラットフォーム構想を立ち上げ、全国規模のビジネス展開を目指していたが、構想の中心メンバーが離脱したことで頓挫してしまった」 と明かした。 崩壊したビジネスモデルに必要なのはイノベーションではなくリノベーションだ。 そして、現在の広告業界に必要なのもイノベーションではなくリノベーションだと、高広氏は考察する。 「現在のアドテク業界には、革新的な技術開発(イノベーション)よりも、既存システムの改善・改良(リノベーション)が必要だ。近江商人の「三方良し」の精神のように、広告業界では、ユーザー、パブリッシャー、広告主という三者の利益のバランスがとれたエコシステムが構築されることが理想であり、アドテク事業者は、この三者の均衡を保つ役割を担うべき存在である。だが、現状は特定のプレイヤーに偏っているアドテク事業者が多い。これが現在の広告業界に様々な問題が生じている理由のように思える。 この問題を解決するために、1つの事例を紹介する。昔、検索窓にキーワードを入力すると、30日以内に検索結果を郵送するというGoogleのパロディサービスを行った人がいた。このサービスは一見時代遅れのようだが、Google の本質的な機能、つまり「情報を提供する」というミッションを捉えていると言える。 この事例から学べることは、技術の進化に囚われず、自らのミッションの本質を見極めることの重要性だ。たとえ古い技術を用いたとしても、本質を捉えていれば価値を提供できるはずだ」 もっと面白い広告を作るべし! セッションの最後には高広氏と野下のQ&Aが行われた。 まず野下から「邪魔な広告の既視感」について聞かれると高広氏は 「今、ユーザー体験を阻害する広告と言えば動画の合間に出てくる広告やポップアップ広告ではないでしょうか? 昔もJavaScriptをオンにしておくと画面いっぱいの広告が出ました。当時はあまりにもそのような広告が出すぎて、ワームやトロイの木馬のように、広告がマルウェアみたいに扱われてしまった時代がありました。今、またその歴史を繰り返しているのではないだろうか」 続いて「ユーザーにとって有益な広告とは?」という質問に対しては ユーザーにとって興味、関心があるタイミングで表示される広告、そしてユーザーが見たくなる広告を挙げた。 「広告が邪魔になる理由を端的に言えば“面白くないから”。YouTubeやTikTokで流れる広告をユーザーが邪魔に感じる理由は、観ているものより広告の方が面白くないに尽きるでしょう。ただ、昔もテレビでCMが流れている時間は“トイレタイム”と言われていて、ユーザーにとっては嫌われていた。だからこそ、CMクリエイターたちは観てもらえるように、面白いCMを作る努力をしていた。ところが今はどうか。みなターゲティングでリーチすることばかり考えていて、広告のクリエイティブを軽視している。面白い広告ならば、アテンションも必然的に上がる。それが広告の本質だと思う」 と述べた。 最後に「先ほど高広氏がおっしゃったアテンションと、今新しく出てきた指標であるアテンションは、相互作用するものなのでしょうか?」という質問には 「“アテンション”という言葉には、一般的な意味や心理学的な意味、そしてデジタル広告業界で使われる意味と、様々な解釈が存在する。デジタル広告業界で使われるアテンションにおいてはまず、定義を整理する必要があるだろう。広告業界でアテンションを扱う際、アテンションをどのように定義するかは、効果測定の観点から共通認識を持つべき重要な課題だ。 しかし、心理学や一般的な意味でのアテンションについても今一度考える必要がある。 一般的にアテンションとは“注目される”ことであり、注目されるためにはどうすれば良いかを考える必要がある。つまり、アテンションを上げるためには、注目を集めるための施策が不可欠だ。 心理学には“選択的注意セレクティブアテンション(選択的注意)”という言葉がある。これは、カクテルパーティーのように騒がしい環境でも、自分に関係のある会話は自然と耳に入ってくる現象で『カクテルパーティー効果』とも呼ばれる。 効果的な広告を作るためには、このセレクティブアテンションを誘発するようなクリエイティブや広告の出し方を考える必要がある。つまり、広告指標としてのアテンションと、人間の心理学的側面から見たアテンションは分けて考えるべきだ。そうすることで、より効果的な広告を展開することが可能になるだろう」 と締めくくった。
アテンションを活用した革新的キャンペーン事例 電通デジタル×Teadsが切り拓く新時代の広告戦略[インタビュー]
デジタル広告の進化に伴い、従来の広告表示回数やクリック率といった指標に加え、ユーザーが実際に広告を目にしたかどうかを示すアテンション指標の重要性が増している。ただ日本国内ではまだ一部の先進的な広告主のみが導入している状況にあるため、その利用実態は見えづらい。そこで電通デジタルとTeadsが共同で実施した国内企業ブランド向けキャンペーンを通じて、アテンション指標がいかに活用されているかを探った。 国内標準がまだない新指標 -自己紹介をお願いします。 高塚氏:電通デジタル第3アカウントプランニング部門第2事業部の高塚健太郎と申します。クライアント企業が抱える様々な事業課題の解決に向けて、メディアプランニングを含めたご提案をしています。 金澤氏:Teads Japanでアカウントエグゼクティブを務める、金澤史帆と申します。電通デジタル様をはじめとする大手広告代理店企業とのお取引を担当しています。 -両社がアテンション計測を実施したキャンペーンの概要についてお聞かせください。 高塚氏:商品のブランド認知拡大に注力するクライアント企業からのご要望を受けて、ユーザーにしっかりと視認される広告の配信方法を改めて精査していた際に、Teads様よりアテンション計測とその結果に基づく広告クリエイティブの改善策をご提示いただけるとのご提案を受けました。 Teads様から、アテンション計測の事例をご紹介いただいており、その中でアテンション指標とブランドリフトが連動するということを伺っておりました。 今回のキャンペーンでもアテンション指標の向上に努めることで、最終的にはブランド認知拡大につなげることができると考えました。 金澤氏:タッチポイントの増加などを受けて、ユーザーが一つ一つの広告に接触する時間は減少傾向にあります。つまり、きちんと見られていない広告が増えているのです。こうした環境下においては、「広告が見られている可能性がある」ことを示すに過ぎないビューアビリティや広告視聴時間といった従来の指標だけでは不十分です。そこでTeadsでは、広告がしっかりと見られたことを示すアテンション指標を開発したLumen Research社と提携することで、アテンション計測が可能な環境を整備しました。 現在はTeadsのネットワークにつながるすべての配信面でアテンション計測が可能です。インプレッションやクリック測定と同じようにアテンションを計測できる機能が初期設定として搭載されています。 -アテンション計測の実施に対して広告主はどのような反応を示しましたか。 高塚氏: そのクライアント企業は以前からブランドセーフティやアドベリフィケーションに高い関心を持ち、とりわけビューアビリティは注視していたので、アテンション計測に対しても前向きに取り組んでいただきました。 当社よりご提案した時点では、アテンション計測という言葉自体にはあまりなじみがなかったようです。しかしながら、概要を説明すると、これまで抱えていた課題に取り組む上で、アテンション計測が一助になるとご判断いただきました。 -その広告主にとっては初めてとなるアテンション計測を実施する上でどのような準備や整理を行いましたか。 高塚氏:先ほど金澤さんが仰ったように、Teadsのネットワーク上であれば計測自体は特に準備することなく実施可能なのですが、アテンション指標になじみのない企業としては、「良い/悪い結果でした」という報告とともに数値だけを示されても判断に困ります。初めての試みなので、そもそも比較対象となるベンチマークがなく、評価ができないからです。 そこで、まずはアテンション指標の基本的な概念から説明することに加えて、Teads様には「広告のどの部分にユーザーの視線が集まっているのか」という分析結果を提供してもらいました。広告クリエイティブのどのような要素が最もユーザーの注目を集めるのかという点はこれまで推測するしかなかったのですが、アテンション計測を通じて可視化されたことで、クライアント企業からは大変参考になったとの声をいただきました。 -その広告主にとっては初めての試みだったとしても、アテンション指標の業界標準的なベンチマークはあるのではないでしょうか。 金澤氏:アテンションは新しい指標なので、国内の業界標準がまだ出来上がっていません。米国や欧州といった先進的な市場はデータを蓄積しつつありますが、日本と欧米ではアテンションスコアが大きく異なるケースも多く、日本のクライアント企業にとってはあまり参考になりません。 昨年より本格的に国内にてアテンション計測をローンチいたしましたが、日本国内のベンチマークを設定できるよう、現在データの収集・整備を進めております。業界ごとの、ベンチマークを算出するという点においては、今後も継続したデータの収集が必要と言えます。 アテンションスコアをいかに分析・活用するのか -今回実施したキャンペーンにおけるアテンション計測の結果を教えていただけますか。 金澤氏:新商品の訴求を目的として、同じ構成でテキストのみ異なるクリエイティブを3種類ご用意頂きました。その中で、特定の1つだけ目立ってアテンションスコアが高いものがありました。 また、本キャンペーンではブランドリフト調査も実施したのですが、そこでも同じクリエイティブが最も高いブランドリフト効果を示していました。ブランディングキャンペーンにおいては、ブランド認知は向上したけれども、購入意向が上がるまでには至らない場合もあるのですが、今回は購入意向も上昇しています。 さらに今回はキャンペーン実施前に、表示された広告に対するユーザーの目線の位置をAI分析機能を通じて推定したところ、すべてのクリエイティブで、ほぼ同様にテキスト部分に目線が合っていました。つまりテキストないしはコピーが違いを生み出したということになります。 高塚氏:その点は非常に興味深く感じました。特定のクリエイティブだけ突出して認知から購入意向まで向上することは珍しいのではないかと個人的には思います。 -アテンション計測の結果はどの段階で把握できるのでしょうか。 金澤氏:インプレッションなどと同時にTeads Ad Manager上(広告管理画面)でご確認いただけます。従って、キャンペーン実施期間中にアテンションスコアを確認しながら、クリエイティブを変更していくことが仕組み上は可能です。 しかし、現時点ではアテンション指標とブランドリフト効果の相関性を証明するためのデータについては蓄積中の段階であるため、今後両者の相関性が確認できたタイミングでアテンション指標に基づく最適化をご案内できたらと考えております。 高塚氏:アテンション指標については我々のような立場でもまだまだ理解を深めていく余地が残っていると感じています。ただし、今回のようにブランド認知とブランドセーフティを重視されるクライアント企業には、アテンション指標は非常に相性が良いとの印象が強まりました。 -アテンション計測全般において課題に感じることはありますか。 金澤氏:業種ごとにアテンション指標の平均値は異なることが想定され、例えばエンターテインメント商材とB to B商材ではスコアが大きく異なる可能性があります。 今後、日本で業界別やキャンペーンの種類別にアテンションとブランドリフトとの相関性を見出すことができれば、広告最適化を行う上で重要なデータになると考えています。 高塚氏:ここまで広告プラットフォームとクライアント企業の視点からお話してきましたが、その先にいるのは生活者ないしユーザーです。アテンションスコアが高い広告がユーザー体験を毀損してしまう可能性については十分に留意すべきだと思っています。今後はユーザー目線でのアテンションスコアの精査も行っていきたいです。 日本市場への普及の見通し -日本国内におけるアテンション指標の導入状況はいかがですか。 金澤氏:既に申し上げた通り、Teadsのネットワーク上ではすべてのクライアント企業及び広告代理店様がアテンションスコアを確認いただけます。しかしながら、全キャンペーンでアテンション指標が重視されているわけではないと思います。 高塚氏:先行している米国や欧州市場に倣い、日本でもアテンション計測を積極的に導入している外資系のクライアント企業はいらっしゃいます。国内の企業に対しては、まずはアテンションという概念の説明から必要とされる場合が多い印象です。 ただし、ブランドセーフティという概念も、国内で話題を集め始めてから浸透するまでのスピードは非常に速かったと記憶しています。アテンションも同様の広がり方をするのではないかと想像しています。 ―アテンション指標に対する期待をお聞かせください。 高塚氏:アテンションスコアをただ示すのではなくて、「商品の認知にどのようにつながったのか」「特定の媒体におけるこのような施策はアテンションが高い」といった分析や知見とともにクライアント企業にお伝えできるようになることを目指しています。アテンションスコアとブランドリフト効果の相関性が確認できたとしても慢心せず、アテンション指標に基づくと、どういったセグメントのユーザーに対してどのようなクリエイティブ手法があるかなどを継続的に検討できたらと思います。 金澤氏:当社のような広告プラットフォームは、絶え間ない環境変化に応じて、最適な機能を提供し続ける必要があります。Teadsは、その一環としてのアテンション指標の推進を含めて、常に最適なソリューションをお届けできるプラットフォームでありたいと思います。
リテールメディア市場成長のキーワード「ノンエンデミック広告」 EC事業拡大を後押しする新たな付帯収益獲得
EコマーステクノロジーのリーディングカンパニーであるRoktが2024年11月21日に開催した『The Future of Ecommerce Summit』(通称:Rokt FES)にて、Rokt ビジネス開発 ディレクター 大野皓平氏とExchangeWireJAPAN副編集長で株式会社デジタルインファクトの執行役員 長野雅俊が登壇した。 本記事では、登壇において発表された、Roktと株式会社デジタルインファクトが共同で行った、国内初のノンエンデミック広告市場に関する調査報告の様子をレポートする。 (Sponsored by Rokt) リテールメディアの新潮流『ノンエンデミック広告』とは? まず、本セッションにおけるエンデミック広告とノンエンデミック広告の定義を解説する。 エンデミック広告とは、リテールメディア広告の一形態であり、媒体となるメディアやプラットフォームの主要なテーマやコンテンツに関連する内容を表示するものである。一例として、ファッションサイトに掲載される靴やバッグの広告や、ショッピングサイトのスポンサードプロダクト広告が該当する。 ノンエンデミック広告もまた、リテールメディア広告の一形態であり、特定のECサイトやアプリ上で商品やサービスを販売していない企業が、そのECサイトやアプリ上に出稿する広告である。一例として、ファッション/航空券/チケット/デリバリーサービスなどの販売を行うサイトやアプリ上に、ヘルスケアECサイトや音楽配信サイトなどの広告が掲出される事例が該当する。 長野はノンエンデミック広告に関して「日本ではまだ馴染みの薄い言葉ですが、米国市場では既にノンエンデミック広告市場が形成されつつあり、今後日本でも大きく発展する可能性が高い領域です」と報告。 そして、調査レポートでは、2023年の日本国内でのノンエンデミック広告市場は424億円で、この数字が5年後には約4倍の1693億円にまで成長すると予測している。 長野はこの予測について、10年ほど前から成長してきた動画広告市場およびインフィード広告市場の動向と、ノンエンデミック広告の類似性を指摘し、 「10年前、顧客体験の悪化が懸念された動画広告や、意味の説明から始まったインフィード広告が、日本国内で1000億円を超える市場規模に成長しました。ノンエンデミック広告も同様の成長を遂げる可能性が高いと考えられ、レポートで予測された2028年の1693億円という数値は現実的であると認識しています」と述べた。 また、長野が「ノンエンデミック広告に相当する広告を多数取り扱っているRoktとして、2028年の1693億円という数字をどう認識しているか」と質問したのに対し、Roktの大野氏は、Roktが取り扱う広告の増加や引き合いの多さ、エンデミック広告を行うEC事業者からのノンエンデミック広告に関する相談の増加なども理由に挙げ、ノンエンデミック広告に関するニーズが増加しているという見解を示した。 「そして何より、2023年のRokt FES参加者が40名弱だったのに対し2024年は2倍以上の方に参加いただきました。これは、ノンエンデミック広告の注目度が高まっている理由ではないでしょうか?」と笑顔で答えた。 続いて長野は本調査において、ノンエンデミック広告の年間平均成長率を300%と予測したことを紹介し、その理由として市場に大きな伸びしろがある点を挙げた。 現状、大手ECモールや一部の先進的な独立系EC事業者を除き、多くの事業者はまだノンエンデミック広告に取り組んでいない。今後、先進的な独立系EC事業者が成果を上げれば追随する企業が必ず現れ、市場が大きく成長していくと強調した。 ECサイトと広告主、双方にメリットをもたらす ノンエンデミック広告の可能性 上記でノンエンデミック広告市場の伸びしろについて言及したが、長野はさらに3つの理由で、ノンエンデミック広告市場が成長する理由を紹介した。 1つ目は利益率である。 ノンエンデミック広告は基本的に広告取引コストのみが発生するため、規模が小さくても、利益率を考慮すれば事業者にとって見逃せない付帯収益となる。 2つ目は商流への非依存性である。 エンデミック広告の場合、ファッションECサイトであればファッション関連の広告が配信されるため、取引先との関係性などを考慮する必要がある。一方、ノンエンデミック広告はECサイトとの関連性が低い広告を配信できるため、商流に影響を与えることがない。 3つ目は、高額な広告費を持つ事業者の広告を配信できる可能性である。 2つ目と重複する部分もあるが、ノンエンデミック広告であれば関連性の低い広告を配信できるため、例えばファッションECサイトであっても、広告費の大きい自動車、金融商品、不動産、世界規模の動画プラットフォームなどの広告を配信することが可能となる。 さらに広告主側から見たノンエンデミック広告の魅力についても解説した。 ECサイトの購買データは、広告主にとって極めて価値の高い情報である。ノンエンデミック広告を通じて、自社で販売している商品と直接関係のないECサイトの購買データを取得できれば、マーケティング戦略の精度を大幅に向上させることができる。 加えて、リテールメディアの進化も見逃せない。従来のカスタマージャーニーでは、消費者はGoogleなどで商品の口コミを確認し、購買を検討する時間が大半を占め、実際に商品を購入するECサイトに滞在する時間はごくわずかだった。しかし、各ECサイトがリテールメディアに注力することで、サイト内で商品の口コミを確認し、購入を検討し、そのまま購入に至る流れが確立されつつある。この変化により、ECサイトへの滞在時間が延び、広告出稿のメリットも一層高まっている。 そのうえで長野は、ノンエンデミック広告のネガティブな側面についても言及した。 「ノンエンデミック広告を推進する際には、以下の点に注意が必要です。第一に、自社プラットフォームで取り扱いのない商品を宣伝することになるため、広告のターゲティング精度が重要となる。第二に、ECサイトによってはブランドイメージを重視する傾向があるため、広告クリエイティブや掲載商品の選定には十分な注意が必要です」 大野氏もノンエンデミック広告市場拡大において配慮するべきこととしてユーザー目線の重要性を指摘した。 「ECサイトで興味のない商品や広告が表示されると、ユーザーの購買体験を損ね、ブランド毀損につながる可能性があります。また、広告が原因で離脱されるという本末転倒な結果を招く恐れもあります。Roktは、EC事業者、ユーザー、広告主にとって三方良しのソリューションを提供することで、こうした課題に対応していきます」 ノンエンデミック広告が リテールメディアの新時代を切り拓く 最後に大野氏から「ノンエンデミック広告が発展していくうえで重要なキーワードは?」という質問に対し長野は3つのキーワードを紹介した。 1つ目は、本業とのシナジーである。 ECサイトのメイン事業は販売事業であり、それを妨げるような広告事業はあってはならない。ノンエンデミック広告を展開するとしても、そこで得た広告収入は、ユーザーへの還元やサービス向上に充てるという意識が重要である。 2つ目は、Scalability(拡張性)である。 個々のECサイトが単独で広告主の要求を満たすのは困難な場合が多いため、ECサイト同士が連携し、拡張性の高いネットワークを構築することで、広告主の多様な需要や要望に応えられるようにする必要がある。 3つ目がレレバンシー(興味・関心)である。 ECサイト上で販売していない商品の広告を無差別に表示するだけでは、ユーザー体験を損ない、サイトからの離脱を招きかねない。そのため、ユーザーのニーズに寄り添い、受け入れられやすい、関連性の高い広告をいかに配信できるかが、ノンエンデミック広告成功の鍵となる。 ノンエンデミック広告は、高い収益性や柔軟性、大手広告主との連携など、大きな強みを備えており、日本市場での急成長が期待される新領域だ。 ノンエンデミック広告に興味のある方は、Roktが公開している、「ノンエンデミック広告がリテールメディアの新時代を切り拓く」と、ExchangeWireJAPANの記事をぜひご拝読していただきたい。
ExchangeWire-ザ・談会 ストリーミング広告の今とこれから-
志(こころざし) 越えてつながる 春の波 ストリーミング広告(=インストリーム動画広告)の需要は、かつてないほどの高まりを見せている。 コネクテッドテレビの普及により存在感がますます高まる中、広告主にとって、ストリーミング広告はどのような位置づけになりつつあるのか。またプログラマティック取引により、今後ストリーミング広告でどのようなことが実現できるのか。 ストリーミング広告の今とこれからについて、お話を伺った。 福原 夕佳氏 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ メディアビジネス本部 パフォーマンスデザイン局 局長 土屋 尚氏 株式会社フジテレビジョン 技術局 デジタルメディア技術部 担当部長 広告配信サーバー管理 香川 晴代氏 Index Exchange Japan株式会社 日本担当 マネージングディレクター -皆さまのビジネスにおけるインストリーム広告との関わりについて、お聞かせください。 土屋氏:フジテレビの技術局(営業局にも兼務中)で、TVerとFODのインストリーム広告枠の管理をしています。広告サーバーの管理業務や広告在庫をどのような配分でどのような取引形式で売っていこうかという販売戦略の策定を行っています。 福原氏:メディアビジネス本部に所属し、広告主であるクライアントに対して、デジタルメディアの運用戦略から実行までをコンサルティングしています。ストリーミング広告においては日々Googleをはじめとするプラットフォーマー各社と連携しながら、YouTubeや運用型広告のTVerなどのプランニングをしております。 香川氏:グローバルのアドエクスチェンジ事業者として、ストリーミング広告の技術開発に関わっています。ストリーミング広告とは切り離すことが出来ないコネクテッドテレビ領域への注力をしています。2024年の米国のコネクテッドテレビ広告市場は前年比21.7%増、約287億ドルと、巨大な規模に達しています。 日本の市場に関しては、私たちは海外で蓄積した色々な知見、ベストプラクティスを提供していこうとしています。業界の啓蒙活動の一環として、「Index Explains」という動画シリーズを通じて、ストリーミングTVの動画広告について分かりやすい解説を共有しています。 -ストリーミング広告の市場シェアは圧倒的にYouTubeが持っており、そこにTVerやABEMAが追随する構造になっています。福原さんに伺いたいのですが、広告主は各媒体にどのような意識でストリーミング広告を出稿しているのでしょうか。 福原氏:YouTubeは国内で最も多くのユーザーを抱える動画プラットフォームであり、幅広い層へのリーチを目指す広告主にとって最重要の選択肢とされています。 一方で、TVerやABEMAはエージェンシーのプランニングツールを用いてリーチ効率を比較すると、YouTubeに劣る傾向があります。そのため、これらの媒体はリーチ効率よりもコンテンツの質を重視するプランニングにおいて選択されることが多いと考えられます。 これらの媒体とYouTubeの大きな違いは、ユーザーの視聴態度にあるのではないでしょうか。YouTubeには、従来のテレビ視聴のように、目的を持たずに動画を視聴する傾向が見られる一方、TVerやABEMAは特定のコンテンツを目的として視聴されるため、ユーザーのエンゲージメントが高いと考えられます。広告主は、このような視聴態度の違いを考慮し、広範なリーチを目的とする場合はYouTubeを、コンテンツとの関連性を重視した広告出稿を行いたい場合はTVerやABEMAを、といったように使い分けているのではないでしょうか。 -TVerやFODにストリーミング広告を出稿する広告主は、どのような意識をもってしているとお考えでしょうか? 土屋氏:おかげさまでTVerやFODの売上規模もどんどん成長してきています。新規のお客様も非常に増えています。広告主の皆さまに認知頂いており、プランニングにも含めていただいていることが増えていると実感しています。 ブランドセーフティの意識の高まりと共に、TVerであればテレビと同じコンテンツに出稿するということですので、出稿先への不安はないということについて、直接広告主の方からもお声をいただくこともあります。 -日本の広告主と海外の広告主と比較した時、何か意識の違いについてお気づきの点はありますか? 香川氏:海外ではプログラマティックの技術導入が進んでいます。テクノロジーを活用して、テレビのストリーミング広告を出稿していくということを、海外の広告主は積極的にやっています。特にテレビに広く出稿することが自由にできない中小広告主であっても、プログラマティックであれば、特定領域に集中して投資をすることが可能です。可能な予算範囲でターゲティングニーズにかなう範囲での手法として広がってきています。また、グローバルでは、広告主、放送局をはじめとする媒体社の双方がプログラマティックの導入を加速させています。 一方で、日本はまだこれからであるという認識をしています。 福原氏:TVerをプログラマティックで買い付けする場合には、第三者のデータを使うことが出来ますので、TVerでターゲティングをすることについては根付いてきているのかなと思います。 -TVer側でも、ターゲティングが出来る環境を進めているのでしょうか? 土屋氏:そうですね。ターゲティングは大きく二つあります。一つはオーディエンスターゲティングです。そして、もう一つはコンテンツターゲティングですが、この領域で新しい取り組みとして進めているものがあります。我々はコンテンツ情報を一次情報として保有しており、コンテンツ情報を開放していくというものです。例えば、コンテンツのジャンル、サブジャンルのようなものから、最終的には演者の情報などもです。あるいは、そのコンテンツにどのようなシーンがあるのかなどの情報を付与する事でコンテキストターゲティングも可能にななります。コンテンツの中身に関する情報をしっかりと整理していって、これを使って広告枠の買い付けを行って頂ける様な取り組みを進めています。 背景として、純広告で我々が「演者マッチング」と言っているメニューが非常に人気な事があります。これは、CMに出演している演者が主演、助演をしているドラマコンテンツへコンテンツターゲティングする事により広告のパフォーマンスを上げる事ができる物です。視聴者は該当の演者をチェックしてドラマを視聴しており、当然その広告も忌避感なくしっかりと見て頂けます。このようなものは、UGCでは難しい取り組みであり、差別化という意味で我々としても力を入れているところです。 普及するコネクテッドテレビが変える、ストリーミング広告の出稿環境 ―コネクテッドテレビは今日本でも普及が進んでいますが、広告の量はどのくらい増えているのでしょうか。 土屋氏:今TVerでは、本篇の再生数ベースですと約3割がコネクテッドテレビ経由で視聴されています。一方、広告配信サーバー側から在庫量ベースでみると、既に全体の4割を超えていますし、今後も増え続けるでしょう。これはスマホやPCなどよりもコネクテッドテレビ視聴のほうが、より長く視聴されますので、本篇1再生当たりの広告在庫ボリュームは多くなる事が起因しています。 -広告主側は、配信先をコネクテッドテレビに指定をして出稿をするようになっていますか? 福原氏:基本的にどの広告主もコネクテッドテレビを含めて配信しています。当社が実施した配信結果を調べてみても、YouTubeの場合には今はデバイスを指定しなくとも、4割を超える割合でコネクテッドテレビに配信されています。 コネクテッドテレビに限定するかどうかは、キャンペーンの設計によって異なると考えられます。 デバイスをコネクテッドテレビに限定することは、リーチやコンバージョンなどの機会損失につながるため、あえてデバイスを絞り込むメリットは少ないと言えるでしょう。 テレビCMと同じ役割でストリーミング広告を活用する場合は、画面占有率の高いコネクテッドテレビに限定してYouTubeやTVerへの出稿をする広告主も一定はいらっしゃいます。 -効果測定は今どのようにしているのでしょうか? 福原氏:デジタル中心のキャンペーンにおいては、従来のスマートフォンやPCといったデバイスと比較して、コネクテッドテレビがもたらす効果の大きさに改めて注目しています。特に、その高い画面占有率が、広告の視認性や記憶への定着に大きく貢献していることが、弊社の比較調査からも明らかになっています。 近年では、テレビCMと比較評価したいという広告主のニーズが顕著になってきており、 当社でもREVISIOを活用して注視率を計測することが増えています。 コネクテッドテレビの場合は、このコンテンツを見に行くという意識でユーザーが視聴するため、テレビCMよりも注視率は高いという弊社の調査結果も出ています。 土屋氏:コネクテッドテレビはスマートデバイスとは環境が異なり、クリックスルー等の直接的なコンバージョンを得ることが出来ないデバイスです。パフォーマンスのレポートについては、Adjust、AppsFlyerのようなパートナーとの連携など、対応を進めています。 -欧米ではどのような状況なのでしょうか? 香川氏:コネクテッドテレビにおける計測の標準化はまだ出来ていません。どこの会社の手法をメインとするかについては、様々な議論が続いています。大手の計測会社が提供するサービスもあれば、複数の大手メディア企業が一緒になって提供をしている計測サービスもあります。 先ほど福原さんがおっしゃったように、テレビCMからの広告主と、デジタル広告からの広告主とでは計測に対するニーズも異なっています。 それぞれに応じたサービスを提供するベンダーが存在するという状況です。 広告主がリーチしたい人に、より透明性を持ってリーチするのかということについては、私たちは媒体と直接つながっている立場として、出来るだけたくさんの情報をバイサイドに届けるよう努めています。ログレベルでのデータを提供しているため、いつどのような広告枠を購入しているかを正確に把握できます。 また、色々なデータを活用して、広告効果を測定をしていくような取り組みも行っています。 例えば、ターゲティングをして、当てたい人に当たっているのかどうかを測る目的で、媒体社から様々なシグナルを受け取る技術を採用していますし、これが精度の高い計測につながっています。例えば、番組のコンテンツジャンルやレーティング、ライブストリームの有無、言語、番組名、シーズン数、放送回タイトルなどの番組単位の情報がこれに含まれます。 ストリーミング広告の今後と、プログラマティックの可能性 ―ストリーミング広告は媒体の選択肢が限られていたことが、課題にもなっています。 福原氏:状況は変わりつつあります。AmazonPrimeVideoでのインストリーム広告の提供が、欧米で始まりました。日本においてもこの4月からプライム会員を対象に広告表示がスタートしました。 香川氏:その他にも、NTTドコモのLeminoや楽天のRチャンネル、グローバル企業のパラマウントとWOWOWとが提携をして、日本でParamount+の提供を開始しましたね。このように、選択肢は増えつつあります。地上波広告のプログラマティック取引が日本テレビでこの春からスタートするのは目覚ましい動きとして注目されています。 福原氏:FAST(Free Ad-supported Streaming Television)のビジネスモデルを社名に冠した「FASTチャンネル」社は、昨年サービスを開始しました。 土屋氏:FASTに関しては、日本でサービスを拡大していくうえで、日本固有の参入障壁が存在するのではないかと考えています。 欧米でFASTが盛り上がりを見せた背景には、無料で視聴可能な形で、過去に制作された人気コンテンツを再活用し、ユーザーがCTV上でザッピングしながら気軽に楽しめる環境が、それまで存在していなかったという点があります。 さらに、新型コロナウイルスの影響により家庭内での可処分時間が増加したこと、そしてインフレの影響によってユーザーが新たなサブスクリプションサービスへの加入を避ける傾向が強まったことも、FASTの成長を後押しした大きな要因であると考えております。 ですが日本にはもともと無料で気軽に楽しめる地上波テレビがあり、そのジャンルのカバー範囲は広く、コンテンツはまだまだ強いです。供給力をみても、新たに日本オリジナルでチャンネルサービスを開始し一定のレベルを維持するということは、容易ではありません。絶えず一定レベルの新作コンテンツを作り続ける体力があるコンテンツ事業者はなかなかいませんし、欧米の様に過去作を上手く使おうと思って複雑な著作権処理をしっかりと行った上で大量にコンテンツを揃える事は日本の環境では難しく思います。 更に収益性の観点で見ても、日本では、今のところUGCと言われているメディアと、プロコンテンツのメディアとがはっきりと差別化されていません。我々は定性的な説明だけでなく定量的にパフォーマンスに差がある事を証明し続けなければいけないと思います。 香川氏:UGCとプロコンテンツに、相応の対価を払い分けるということは海外では一般的なことです。プロフェッショナルコンテンツと、UGCと同じCPMで諮るということはしません。私がこの話を海外の同僚にすると、「質の異なるコンテンツに対して、それぞれ相応の対価を払うのは当たり前のことであり、なぜそのようなことが議論になるのかわからない。」と言われます。 福原氏:これは日本のデジタル広告市場における特有の課題、あるいは私たち広告会社が向き合うべき課題なのかもしれませんが、「1インプレッション単価の価値」に対する議論が深まらない現状があります。YouTubeであろうとTVerであろうと、一律の価値として捉えられ、プランニングが進められているケースが散見されます。背景には、日本の広告主の、ある意味で徹底したパフォーマンス重視の姿勢があると考えられます。「より安価に、より広範囲にリーチできること」が、依然として重要な指標として捉えられているのではないでしょうか。 この点は外資系の広告主は、例えばブランドセーフティの観点からUGCには出稿しないといった、厳密なルールを設定するケースもあり、コンテンツに対するこだわりを持っていらっしゃいます。 土屋氏:地上波テレビとYouTubeのクロスメディアプランニングは1つのパターンになっていますが、 地上波テレビとYouTubeとでは、コンテンツや視聴体験の同質性がない中で、福原さんが仰っている通り可能な限り安価にリーチを補完するというというものです。 今はTVerも広告在庫が増加してきておりますし、広告主の方にプレミアムなAVOD広告枠の価値を評価頂ける様に努めています。 ―放送局がTVCMをプログラマティックでバイイング出来るサービスを開始しましたが、今後TVCMでもプログラマティックバイイングが主流になるのでしょうか? 土屋氏:広告枠が有限、固定的である以上、主流になるとは言えませんが一部の広告枠をデジタル化していくという動きはあると思います。先ほどテレビでターゲティングをするという話がありましたが、欧米ではアドレッサブルと呼ばれる、地上波テレビ広告枠をターゲティング可能にする技術が出来てきています。 本篇の再生は地上波受信によるものですが、インターネット結線されているテレビに対して、広告はインターネット経由で配信されるという物です。 アドレッサブルというのは、まさにこの切り替えをスムーズにして、ターゲティングをすることが出来るという技術です。これについては、徐々にフィージビリティが高まってきておりプログラマティックバイイングを後押しする要因になり得ると思います。 ―現状は寡占化されている日本において、媒体社が広告在庫をオープン化して、プログラマティックで買い付けが出来るようにするインセンティブはどこにあるのでしょうか? 土屋氏:広告業界におけるオープン化というのは聞こえは良いのですが、一方でクリエイティブや視聴体験の悪化に繋がる様な印象が媒体としてはあります。我々はオープンであっても事前にクリエイティブの審査をする必要性があると感じています。この作業はAIの進化によって、かなりスピーディーになり事後審査によるベストエフォートな物と事前審査とのタイムラグを中長期的には改善してくれると期待しています。 これまで、オープンな環境で事後考査もしくは事前審査はしていると言っているが明らかにその精度について疑わしい仕組みが広がったことで、劣悪な体験が増えてしまったのでしょう。そういった環境へそのまま我々がでていくことはないでしょう。 一方で、広告枠のデジタル化というのは広告枠の特性が多様化し枠数も爆発的に増えるという事です。そう考えると中小規模でも、業態やクリエイティブの考査、出稿単価に問題がなければ、我々としては出稿頂きたいと当然考えます。広告主としてもプレミアムな媒体に簡単にアクセスできる事は良いことだとお思います。そうなると結果としてオープンでプログラマティックというのは我々の広告枠を埋めてくれて広告主にもその価値を与えてくれる物になると思います。そういった意味では、オープンだクローズドだという事にあまり囚われるのは良くないのではないかと思います。 香川氏:デジタルの世界では、ディスプレイ広告とストリーミング広告では、フォーマットが異なりますが、ディスプレイ広告において、最初は予約型広告のみで、その後プログラマティック化し、プログラマティックが中心になったように、ストリーミング広告もプログラマティックが主流になっていく点には議論の余地はないと思っています。 メリットは、媒体社からすると圧倒的な数の広告主からの出稿を受けられることや、取引の簡便化などが挙げられます。プログラマティック取引は、標準化された自動入札の取引ですので、マニュアル作業は大幅に軽減されます。将来は、より簡略化された最適な取引として発展していく可能性もあります。 ―プログラマティックに対する期待する点はありますか? 福原氏:香川さんがおっしゃったように、デジタルの良いところを取り入れて、まずは発展していけるのはとてもいいことかなと思います。 香川氏:意外な話かもしれませんが、テレビCMで当たり前にできていることが、逆にコネクテッドテレビではできていなかった、そんなこともあります。テレビCMでは、1つの番組で複数の広告主が入りますが、同業種の競合企業の広告が並ぶことはありません。例えばトヨタ、ホンダ、スズキのCMが連続して出ることはありませんよね。 コネクテッドテレビでは、当初これが出来なかったのですが、技術が確立してできるようになりました。 具体的には、OpenRTB2.6というプロトコルのお陰です。当社では、OpenRTB2.6をIABTechLabと一緒に作ってきました。このプロトコルに含まれる広告Podという技術により、テレビの視聴者や広告主が当たり前と感じている視聴体験をコネクテッドテレビでも実現することが出来るようになりました。 もう一つ海外で今注目を集めているのが、ライブストリーミングです。ライブストリーミングは、どのタイミングでどのくらいのユーザーが見に来るのかが予測できないものです。 視聴者の注目を集める試合のピーク時に、広告出稿の大チャンスが訪れます。 視聴者数が集中した時の大規模な自動広告取引に耐えうる技術的なインフラの開発に、世界の注目が集まっています。当社は業界標準を構築し、これを現実のものとするために貢献していきます。 土屋氏:ライブスポーツは、一部の伝統的で非常に人気なものを除くとインプレッション数の予測が難しく、純広告として枠を販売していくのが難しかったのです。 これをプログラマティックで販売できるようになると、マネタイズがしやすくなることが期待されます。 また、コネクテッドテレビ画面は大きいので、Lバンドや、サイド・バイ・サイドと呼ばれるような、画面にコンテンツと広告が一緒に流れるようなフォーマットの提供がしやすくなります。例えば、一般的にCMが入れにくいと言われているサッカーの試合でも、ゴールが決まったとき、挿入するなどの取り組みが出来るようになります。 そういった意味でも、コネクテッドテレビとプログラマティックで、ライブスポーツのマネタイズの可能性が広がります。 香川氏:国内でもストリーミング広告のプログラマティック取引は着実に伸びていきます。グローバル市場で事業を手掛ける当社としては、欧米市場のベストプラクティスと技術を提供し、国内市場の発展を支える役割を、引き続き担っていきたいと思います。
130周年を迎える東洋経済が『変えること』と『変えないこと』―東洋経済新報社×FLUX対談
創立130周年を迎える東洋経済新報社。「社会を良くする経済ニュース」の配信を行う東洋経済オンラインは経済・ビジネスに特化したメディアとして、確固たる地位を築いている。伝統ある経済紙としてのこだわりと、めまぐるしく変化するメディア環境の中での新しい挑戦について、メディア支援を担うFLUXが話を伺った。本対談は2025年2月 東洋経済新報社本社にて行われた。 (Sponsored by FLUX) 堀越 千代 東洋経済新報社 執行役員 東洋経済オンラインプロデューサー 2006年東洋経済新報社に⼊社。業界記者として⼩売り、化学、外⾷業界などを担当。雑誌『週刊東洋経済』編集部、新規媒体開発担当などを経た後、2017年に編集局を離れ、デジタルマーケティングの領域へ。会員制サイトのプロダクトマネジャー、東洋経済ID施策担当などを担う。2023年4⽉、東洋経済オンライン事業局長、2025年3月から現職。 柳田 竜哉 株式会社FLUX VP of Publisher メディア・マーケティングソリューション本部長 2001年朝日新聞社入社。広告局、デジタルメディア本部を経て2010年より朝日インタラクティブ社に出向。CNET japan・CNN.co.jp等を取締役として統括。2016年に朝日新聞社に帰任し、アドテク・運用型広告の領域に注力。2020年4月にFLUXに参画。 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社が運営する「社会を良くする経済ニュース」を配信する情報配信プラットフォーム。毎⽉約1,000本の記事を公開し、⽉間PVは1億を超える。100人を超える社内記者に加え、様々な分野の有識者といった外部著者のべ400人が、一つの事象に対してあらゆる視点での分析を試み、日々記事を生み出している。 東洋経済オンライン22年の歩みと成長の軌跡 堀越:東洋経済オンラインは2003年にローンチし、今年で22年目となります。今の形にリニューアルしたのが2012年です。社内記者に加えて社外有識者の方々にも記事を書いていただくという体制を確立し、ウェブメディア業界全体の勃興とともに急成長してきました。特にコロナ禍でメディアの需要が急増し、2020年には月間で3億PVを超えるまでに至りました。 ユーザーの拡大とともに広告市場の追い風を受け、業績も右肩上がりで推移してきました。 コンテンツ視点とビジネス視点の融合が求められるフェーズ 柳田:堀越さんは2006年に東洋経済に入社後、記者・編集・新媒体の開発やマーケティングを経て、2023年に東洋経済オンライン事業部が新設されると同時に、事業全体つまり経営面の役職に就かれていますが、東洋経済さんでは編集出身者がビジネス(メディアの経営)を担うのはよくあることですか? 堀越:珍しい方かもしれません。今後も理想としては、コンテンツ制作とビジネスの両方がわかる人を増やしていきたいと考えています。 柳田:コンテンツとビジネスの両方のことがわかる人がメディアの中にもっといるといいなと思います。ベンチャー系のメディアだと、皆が全てに関わるためスピード感が早いなと感じることがありますが、大規模な伝統ある企業ではコンテンツ制作とビジネス視点が分断されがちです。今は、そういった点でも変化が求められる局面にあるのかもしれません。 激変するメディア環境、立ち止まる2024年 柳田:昨今メディア環境が大きく変わってきていますが、現状の事業環境をどのように捉えられていますか。 堀越:インターネットメディアを取り巻く環境はネガティブなことが多いと感じます。以前は記事を出せばユーザーが集まり、広告も出稿されるというビジネスモデルが成り立っていました。しかし、ここ2〜3年でその状況は大きく変わり、「このままではいけない」と痛感しています。 最大の課題は、そもそもニュースサイトを訪れるユーザーが減っていることです。特定の話題で瞬間的にアクセスが増えることはありますが、全体的に見ると特にテキストコンテンツを読むユーザーが縮小していると感じます。 私たちはこの10年間、「よい記事さえ出せばユーザーが来る」状況に慣れてしまっていたのかもしれません。しかしながら、今後このままではいられないため、2024年は一度立ち止まり、会社として「これからのメディアの在り方」について本気で考え直す年にしました。 東洋経済オンラインの再定義と「ステートメント」 堀越:昨年、これまで明文化されていなかった東洋経済オンラインのミッションやビジョンを、「ステートメント」として定義しました。東洋経済新報社では、今から130年前『東洋経済新報』の創刊時に記された「健全なる経済社会に貢献する」という言葉を企業理念として、これまでも各業務にあたる社員それぞれが思いを持って、クライアントやユーザーに向き合ってきました。しかし、改めて事業に関わる人全体で認識を共有するために、言語化するための試みとしてステートメントを作成することにしたのです。 ステートメント策定に際し、定量・定性調査、今置かれている現状や課題のためにやるべきこと、未来に向かってやるべきことをさまざまな部門で考えました。また一度作成したものに対しても全社から意見を募集し、それを細かいところまで反映させました。こうして策定した東洋経済オンラインのミッションは「経済・ビジネスを軸に、あらゆる人々が『よりよい選択』をできるよう手助けし、豊かで健全な経済社会を実現すること」です。 これから新しい提案や取り組みをするとき際には、このミッションに基づいて意思決定をしていきたいと考えています。 「読まれる」だけでなく、「社会的意義のある記事」を 柳田:次に、御社のコンテンツ作りについてお伺いさせてください。先ほどインターネットメディアに訪れるユーザーが減っているというお話がありましたが、コンテンツ作りで課題に感じていることなどありますか? 堀越:コンテンツ作りにおいて、マーケットイン(読者のニーズを出発点としてコンテンツ作成を優先する)かプロダクトアウト(東洋経済が発信したいコンテンツを優先するか)か、これまでたくさん迷い、悩んできています。 記者に対して、ビジネス部門からマネタイズを意識するような枠にはめた指示を出せば、面白い記事が出なくなります。記者のクリエイティビティと熱量がないと良い記事は生まれないんです。 柳田:SNSを中心にインフルエンサーと呼ばれる個人による発信が「バズる」時代に、東洋経済オンラインのように専業記者が発信しているメディアの存在意義についてはどうお考えですか。 堀越:確かに、個人のインフルエンサーが影響力を持つ時代です。しかし一方で、東洋経済オンラインは「まとまり」で運営しているのが強みだと考えています。 個人インフルエンサーのマーケットイン的な発想では、「みんなが知りたいこと」を優先して発信すれば良いかもしれません。しかし、多くの人には読まれないかもしれないけれど「今、書かなければならない」という社会的意義がある記事を出せるのは、やはり東洋経済の強みであり、存在意義なのではないかと思います。 弊社は広く名が知れたスター記者がいるわけではありませんが、130年続いてきたメディアとしての責任と信頼があります。一部の人にしか読まれないかもしれないけれど、社会的に重要な記事を発信し続けることこそ、私たちの役割だと考えています。 柳田:まさに御社で発行されている会社四季報がそうですよね。メジャーな企業だけでは成立せず、どんなに小さな銘柄までも網羅していることが価値であると感じます。個人がメディアのようなこともできるというのは面白い時代でもありますが、「まとまり」の大切さには共感します。 FLUXも顧客であるメディアの皆様に対してSEO関連のサポートをすることがあります。やはり「読まれる記事を書く」というのは基本ではあるのですが、「たくさん読まれるだけの記事」では価値を生み出しにくい側面があります。ビジネスとコンテンツのバランスが重要ですね。 堀越:そのバランスを取るのが、まさに今の課題です。マネタイズを強化しすぎると、熱量のある記事が生まれにくくなる。一方で、取材記者は単なる情報発信者ではなく、クリエイターでもある。収益とジャーナリズムの両立をどう図るか、メディア運営において極めて重要なテーマだと思っています。 新たなチャレンジ、動画コンテンツへの再注力 柳田:最近はYouTube動画にも力を入れていますね。 堀越:そうですね。YouTubeチャンネルは以前からありましたが、2024年から本格的にリスタートしました。現在は月20本程度のペースで動画を配信しています。 YouTubeこそ「見られるもの」が「稼ぎ」となりますが、そこで東洋経済らしさをどう出すのかは懸念としてありました。しかし、テキストを読むユーザーが減少している中で、新しいユーザーとの接点を増やす意味でも動画配信には取り組むべきだと考え、YouTubeに再注力することにしました。 柳田:最近も、とある大企業の合併破談についての解説動画がありましたが、ニュースが出てすぐに動画で配信されていましたね。裏話も入っていてとても面白かったです。 堀越:動画における弊社の強みはスピード感です。記者はずっと最前線で取材をしているため、ニュースが出てすぐに記者が解説することができます。 また、動画のフォーマットも工夫しており、編集長が記者に質問を投げかけ、それに記者が答えるという形を取っています。これは、実は記事作成における編集部の日常的な風景をそのまま切り取ったものなんです。そこにも面白さを感じて頂きたいのですが、弊社としては簡単な打ち合わせをすればすぐに収録できる点も大きな利点ですし、動画には新しい可能性を感じています。 ファンとの関係を強化する取り組み 柳田:今新たに注力している領域はありますか。 堀越:東洋経済オンラインのファンを大事にするためにも、読者に対して然るべきサービスを提供することは今後より注力していきたいと考えています。 直近ではユーザー調査を実施し、「ロイヤルユーザー」の分類を再確認しました。そこには、有料会員と、無料ながら頻繁に訪問してくれるユーザーの両方が存在します。どちらも重要な読者層なので、それぞれに適した価値を提供することが必要だと考えています。その中でも特に有料会員であるユーザーには、より付加価値の高いサービスを提供していきたいという話を、ユーザー調査の結果を元に記者も含めて会社として再確認したところです。 柳田:こういったユーザー調査をすると、コンテンツを作る時にも意識するようになりますし、広告主に対して「こういったユーザーがメインとなるのでそういう広告を出してください」と言えるようにもなりますよね。 広告はきちんとターゲットが合えばとても有用な情報となりますし、IDを活用してユーザー属性を明確にすることで、マーケティング担当者から見ても非常に魅力的なメディアになるはずです。 収益化とコンテンツの質、マネタイズ戦略の多様化 柳田:FLUXでは大小様々なメディアの広告マネタイズをお手伝いさせていただいています。その中でも、東洋経済オンラインさんは、読者や広告主にとっての最適とは何かをしっかりと考えて運用なされている印象です。 堀越:ありがとうございます。運用型広告は、ユーザーと広告主の双方にとって最適な形を常に模索しています。 柳田:特に御社のようなプレミアムなメディアにおいては、ブランドセーフティの確保が広告主にとっても非常に重要ですよね。我々FLUXとしても、広告が適切なコンテンツの中で表示され、読者の信頼を損なわない環境を作ることを重要と考えています。 堀越:特に東洋経済オンラインのようなメディアでは、広告の質や掲載環境がブランドイメージにも直結します。ユーザーはもちろんですが、広告主の期待に応えられるよう、厳格な基準を設けています。 柳田:広告収益は一つの収益の柱であるかと思いますが、そのほかサブスクや記事提供も収入柱になっていますか? 堀越:はい、ただサブスクに関してはまだ発展途上です。というのも、有料読者のみが閲覧できるという、いわゆる記事に鍵をかけただけではサブスクは成立しないと思っています。今後はより一層、読者が「東洋経済の有料会員になりたい」と思える付加価値を提供しなければならないと考えています。 柳田:いい記事ほど鍵をかけたくない(有料読者のみが閲覧できる状況にしたくない)と仰っていたことがありましたがとても共感できました。記事ではないところの付加価値をつけるというのは面白いですね。 堀越:また、もう一つの収入柱である「記事提供」に関しては、記事を生成AIの学習用データとしての販売を始めました。これは単なる収益化というだけではなく、ある種の防衛策とも言えますが、無断利用されないために販売しているという側面もあります。販売先は生成AI事業者のみならず、企業が生成AIを活用する際のデータとしても利用されています。ビジネス領域に特化した日本語データかつ、図表を交えたコンテンツというのは希少であり、東洋経済オンラインの強みを活かすあまり他にはないデータなので有用性が高いと思います。 創立130周年に向けて、東洋経済の未来を語る 柳田:東洋経済新報社は今年11月に130周年を迎えられます。今までと変わらず大切にしていきたいことと、これからの展望をお聞かせいただけますか。 堀越:やはり弊社の強みであり中核は、経済・ビジネスのコンテンツです。この強みを活かしながら、今後も価値あるコンテンツを提供し続けることが重要だと考えています。 また、130周年事業の一環として、サイトのリニューアルも予定しています。実は前回のサイトリニューアルから10年以上が経過しており、これまで小規模な改修は繰り返してきましたが、今回は抜本的な見直しを行います。また、動画コンテンツやサブスクリプションといった新たな要素を本格的に取り入れることも検討しているので、楽しみにしていただければと思います。 柳田:業界全体が厳しい状況にある中で、積極的な投資と改革に取り組まれるのは素晴らしいですね。サイトリニューアルも含め、東洋経済の今後の取り組みをとても楽しみにしています。本日は貴重なお話をありがとうございました。
ニュースレター(WireSync)に登録
ExchangeWire Japanの最新情報を毎週まとめてお届けします



![明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]―ATS Tokyo 2024イベントレポート](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/05/takahiro-main-280x187.jpg)
![アテンションを活用した革新的キャンペーン事例 電通デジタル×Teadsが切り拓く新時代の広告戦略[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/04/teadsmain-280x186.jpg)



![明日の[ネット]広告 変化した消費者とコミュニケーションする方法 [を忘れてしまった業界への一言]―ATS Tokyo 2024イベントレポート](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/05/takahiro-main.jpg)
![アテンションを活用した革新的キャンペーン事例 電通デジタル×Teadsが切り拓く新時代の広告戦略[インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/04/teadsmain.jpg)

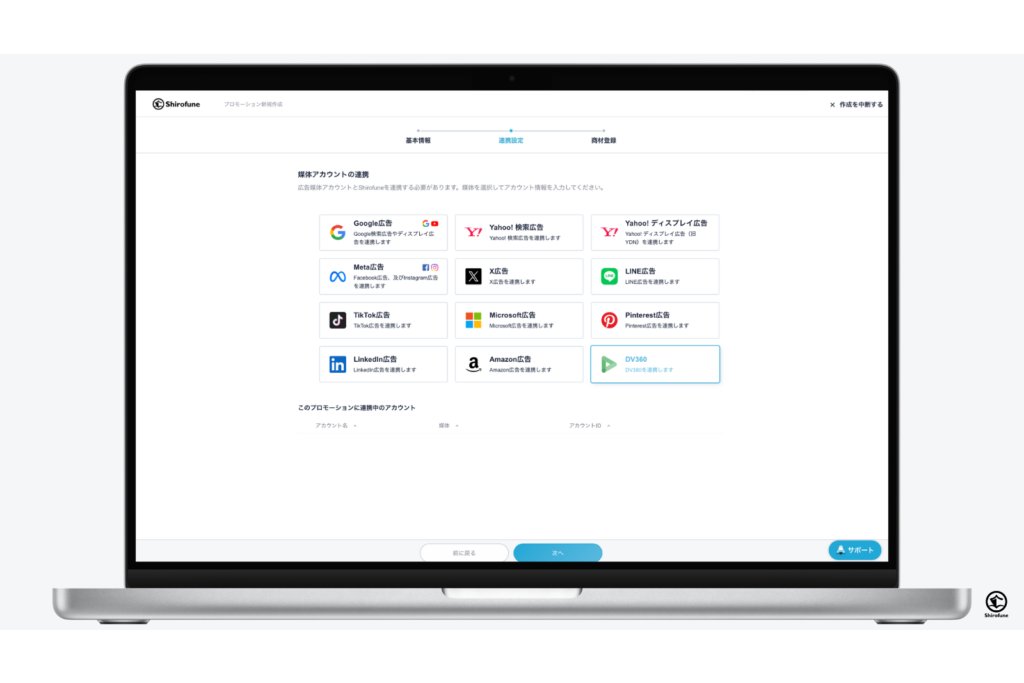

![ユーザー体験を妨げないプッシュ型リワード広告「プッシュリワード」が作る、オファーウォール市場の未来-ADWAYS DEEE×アルファポリス対談 [インタビュー]](https://cdn.exchangewire.com/wp-content/uploads/2025/04/image3-1.jpg)




