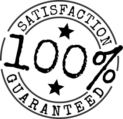ExchangeWire-ザ・談会 ストリーミング広告の今とこれから-

志(こころざし)
越えてつながる
春の波
ストリーミング広告(=インストリーム動画広告)の需要は、かつてないほどの高まりを見せている。
コネクテッドテレビの普及により存在感がますます高まる中、広告主にとって、ストリーミング広告はどのような位置づけになりつつあるのか。またプログラマティック取引により、今後ストリーミング広告でどのようなことが実現できるのか。
ストリーミング広告の今とこれからについて、お話を伺った。

福原 夕佳氏
株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ
メディアビジネス本部 パフォーマンスデザイン局 局長

土屋 尚氏
株式会社フジテレビジョン
技術局 デジタルメディア技術部
担当部長 広告配信サーバー管理

香川 晴代氏
Index Exchange Japan株式会社
日本担当 マネージングディレクター
-皆さまのビジネスにおけるインストリーム広告との関わりについて、お聞かせください。
土屋氏:フジテレビの技術局(営業局にも兼務中)で、TVerとFODのインストリーム広告枠の管理をしています。広告サーバーの管理業務や広告在庫をどのような配分でどのような取引形式で売っていこうかという販売戦略の策定を行っています。
福原氏:メディアビジネス本部に所属し、広告主であるクライアントに対して、デジタルメディアの運用戦略から実行までをコンサルティングしています。ストリーミング広告においては日々Googleをはじめとするプラットフォーマー各社と連携しながら、YouTubeや運用型広告のTVerなどのプランニングをしております。
香川氏:グローバルのアドエクスチェンジ事業者として、ストリーミング広告の技術開発に関わっています。ストリーミング広告とは切り離すことが出来ないコネクテッドテレビ領域への注力をしています。2024年の米国のコネクテッドテレビ広告市場は前年比21.7%増、約287億ドルと、巨大な規模に達しています。
日本の市場に関しては、私たちは海外で蓄積した色々な知見、ベストプラクティスを提供していこうとしています。業界の啓蒙活動の一環として、「Index Explains」という動画シリーズを通じて、ストリーミングTVの動画広告について分かりやすい解説を共有しています。
-ストリーミング広告の市場シェアは圧倒的にYouTubeが持っており、そこにTVerやABEMAが追随する構造になっています。福原さんに伺いたいのですが、広告主は各媒体にどのような意識でストリーミング広告を出稿しているのでしょうか。

福原氏:YouTubeは国内で最も多くのユーザーを抱える動画プラットフォームであり、幅広い層へのリーチを目指す広告主にとって最重要の選択肢とされています。
一方で、TVerやABEMAはエージェンシーのプランニングツールを用いてリーチ効率を比較すると、YouTubeに劣る傾向があります。そのため、これらの媒体はリーチ効率よりもコンテンツの質を重視するプランニングにおいて選択されることが多いと考えられます。
これらの媒体とYouTubeの大きな違いは、ユーザーの視聴態度にあるのではないでしょうか。YouTubeには、従来のテレビ視聴のように、目的を持たずに動画を視聴する傾向が見られる一方、TVerやABEMAは特定のコンテンツを目的として視聴されるため、ユーザーのエンゲージメントが高いと考えられます。広告主は、このような視聴態度の違いを考慮し、広範なリーチを目的とする場合はYouTubeを、コンテンツとの関連性を重視した広告出稿を行いたい場合はTVerやABEMAを、といったように使い分けているのではないでしょうか。
-TVerやFODにストリーミング広告を出稿する広告主は、どのような意識をもってしているとお考えでしょうか?
土屋氏:おかげさまでTVerやFODの売上規模もどんどん成長してきています。新規のお客様も非常に増えています。広告主の皆さまに認知頂いており、プランニングにも含めていただいていることが増えていると実感しています。
ブランドセーフティの意識の高まりと共に、TVerであればテレビと同じコンテンツに出稿するということですので、出稿先への不安はないということについて、直接広告主の方からもお声をいただくこともあります。
-日本の広告主と海外の広告主と比較した時、何か意識の違いについてお気づきの点はありますか?

香川氏:海外ではプログラマティックの技術導入が進んでいます。テクノロジーを活用して、テレビのストリーミング広告を出稿していくということを、海外の広告主は積極的にやっています。特にテレビに広く出稿することが自由にできない中小広告主であっても、プログラマティックであれば、特定領域に集中して投資をすることが可能です。可能な予算範囲でターゲティングニーズにかなう範囲での手法として広がってきています。また、グローバルでは、広告主、放送局をはじめとする媒体社の双方がプログラマティックの導入を加速させています。
一方で、日本はまだこれからであるという認識をしています。
福原氏:TVerをプログラマティックで買い付けする場合には、第三者のデータを使うことが出来ますので、TVerでターゲティングをすることについては根付いてきているのかなと思います。
-TVer側でも、ターゲティングが出来る環境を進めているのでしょうか?

土屋氏:そうですね。ターゲティングは大きく二つあります。一つはオーディエンスターゲティングです。そして、もう一つはコンテンツターゲティングですが、この領域で新しい取り組みとして進めているものがあります。我々はコンテンツ情報を一次情報として保有しており、コンテンツ情報を開放していくというものです。例えば、コンテンツのジャンル、サブジャンルのようなものから、最終的には演者の情報などもです。あるいは、そのコンテンツにどのようなシーンがあるのかなどの情報を付与する事でコンテキストターゲティングも可能にななります。コンテンツの中身に関する情報をしっかりと整理していって、これを使って広告枠の買い付けを行って頂ける様な取り組みを進めています。
背景として、純広告で我々が「演者マッチング」と言っているメニューが非常に人気な事があります。これは、CMに出演している演者が主演、助演をしているドラマコンテンツへコンテンツターゲティングする事により広告のパフォーマンスを上げる事ができる物です。視聴者は該当の演者をチェックしてドラマを視聴しており、当然その広告も忌避感なくしっかりと見て頂けます。このようなものは、UGCでは難しい取り組みであり、差別化という意味で我々としても力を入れているところです。
普及するコネクテッドテレビが変える、ストリーミング広告の出稿環境
―コネクテッドテレビは今日本でも普及が進んでいますが、広告の量はどのくらい増えているのでしょうか。
土屋氏:今TVerでは、本篇の再生数ベースですと約3割がコネクテッドテレビ経由で視聴されています。一方、広告配信サーバー側から在庫量ベースでみると、既に全体の4割を超えていますし、今後も増え続けるでしょう。これはスマホやPCなどよりもコネクテッドテレビ視聴のほうが、より長く視聴されますので、本篇1再生当たりの広告在庫ボリュームは多くなる事が起因しています。
-広告主側は、配信先をコネクテッドテレビに指定をして出稿をするようになっていますか?
福原氏:基本的にどの広告主もコネクテッドテレビを含めて配信しています。当社が実施した配信結果を調べてみても、YouTubeの場合には今はデバイスを指定しなくとも、4割を超える割合でコネクテッドテレビに配信されています。
コネクテッドテレビに限定するかどうかは、キャンペーンの設計によって異なると考えられます。
デバイスをコネクテッドテレビに限定することは、リーチやコンバージョンなどの機会損失につながるため、あえてデバイスを絞り込むメリットは少ないと言えるでしょう。
テレビCMと同じ役割でストリーミング広告を活用する場合は、画面占有率の高いコネクテッドテレビに限定してYouTubeやTVerへの出稿をする広告主も一定はいらっしゃいます。
-効果測定は今どのようにしているのでしょうか?

福原氏:デジタル中心のキャンペーンにおいては、従来のスマートフォンやPCといったデバイスと比較して、コネクテッドテレビがもたらす効果の大きさに改めて注目しています。特に、その高い画面占有率が、広告の視認性や記憶への定着に大きく貢献していることが、弊社の比較調査からも明らかになっています。
近年では、テレビCMと比較評価したいという広告主のニーズが顕著になってきており、
当社でもREVISIOを活用して注視率を計測することが増えています。
コネクテッドテレビの場合は、このコンテンツを見に行くという意識でユーザーが視聴するため、テレビCMよりも注視率は高いという弊社の調査結果も出ています。
土屋氏:コネクテッドテレビはスマートデバイスとは環境が異なり、クリックスルー等の直接的なコンバージョンを得ることが出来ないデバイスです。パフォーマンスのレポートについては、Adjust、AppsFlyerのようなパートナーとの連携など、対応を進めています。
-欧米ではどのような状況なのでしょうか?

香川氏:コネクテッドテレビにおける計測の標準化はまだ出来ていません。どこの会社の手法をメインとするかについては、様々な議論が続いています。大手の計測会社が提供するサービスもあれば、複数の大手メディア企業が一緒になって提供をしている計測サービスもあります。
先ほど福原さんがおっしゃったように、テレビCMからの広告主と、デジタル広告からの広告主とでは計測に対するニーズも異なっています。
それぞれに応じたサービスを提供するベンダーが存在するという状況です。
広告主がリーチしたい人に、より透明性を持ってリーチするのかということについては、私たちは媒体と直接つながっている立場として、出来るだけたくさんの情報をバイサイドに届けるよう努めています。ログレベルでのデータを提供しているため、いつどのような広告枠を購入しているかを正確に把握できます。
また、色々なデータを活用して、広告効果を測定をしていくような取り組みも行っています。
例えば、ターゲティングをして、当てたい人に当たっているのかどうかを測る目的で、媒体社から様々なシグナルを受け取る技術を採用していますし、これが精度の高い計測につながっています。例えば、番組のコンテンツジャンルやレーティング、ライブストリームの有無、言語、番組名、シーズン数、放送回タイトルなどの番組単位の情報がこれに含まれます。
ストリーミング広告の今後と、プログラマティックの可能性
―ストリーミング広告は媒体の選択肢が限られていたことが、課題にもなっています。
福原氏:状況は変わりつつあります。AmazonPrimeVideoでのインストリーム広告の提供が、欧米で始まりました。日本においてもこの4月からプライム会員を対象に広告表示がスタートしました。
香川氏:その他にも、NTTドコモのLeminoや楽天のRチャンネル、グローバル企業のパラマウントとWOWOWとが提携をして、日本でParamount+の提供を開始しましたね。このように、選択肢は増えつつあります。地上波広告のプログラマティック取引が日本テレビでこの春からスタートするのは目覚ましい動きとして注目されています。
福原氏:FAST(Free Ad-supported Streaming Television)のビジネスモデルを社名に冠した「FASTチャンネル」社は、昨年サービスを開始しました。
土屋氏:FASTに関しては、日本でサービスを拡大していくうえで、日本固有の参入障壁が存在するのではないかと考えています。
欧米でFASTが盛り上がりを見せた背景には、無料で視聴可能な形で、過去に制作された人気コンテンツを再活用し、ユーザーがCTV上でザッピングしながら気軽に楽しめる環境が、それまで存在していなかったという点があります。
さらに、新型コロナウイルスの影響により家庭内での可処分時間が増加したこと、そしてインフレの影響によってユーザーが新たなサブスクリプションサービスへの加入を避ける傾向が強まったことも、FASTの成長を後押しした大きな要因であると考えております。
ですが日本にはもともと無料で気軽に楽しめる地上波テレビがあり、そのジャンルのカバー範囲は広く、コンテンツはまだまだ強いです。供給力をみても、新たに日本オリジナルでチャンネルサービスを開始し一定のレベルを維持するということは、容易ではありません。絶えず一定レベルの新作コンテンツを作り続ける体力があるコンテンツ事業者はなかなかいませんし、欧米の様に過去作を上手く使おうと思って複雑な著作権処理をしっかりと行った上で大量にコンテンツを揃える事は日本の環境では難しく思います。
更に収益性の観点で見ても、日本では、今のところUGCと言われているメディアと、プロコンテンツのメディアとがはっきりと差別化されていません。我々は定性的な説明だけでなく定量的にパフォーマンスに差がある事を証明し続けなければいけないと思います。
香川氏:UGCとプロコンテンツに、相応の対価を払い分けるということは海外では一般的なことです。プロフェッショナルコンテンツと、UGCと同じCPMで諮るということはしません。私がこの話を海外の同僚にすると、「質の異なるコンテンツに対して、それぞれ相応の対価を払うのは当たり前のことであり、なぜそのようなことが議論になるのかわからない。」と言われます。
福原氏:これは日本のデジタル広告市場における特有の課題、あるいは私たち広告会社が向き合うべき課題なのかもしれませんが、「1インプレッション単価の価値」に対する議論が深まらない現状があります。YouTubeであろうとTVerであろうと、一律の価値として捉えられ、プランニングが進められているケースが散見されます。背景には、日本の広告主の、ある意味で徹底したパフォーマンス重視の姿勢があると考えられます。「より安価に、より広範囲にリーチできること」が、依然として重要な指標として捉えられているのではないでしょうか。
この点は外資系の広告主は、例えばブランドセーフティの観点からUGCには出稿しないといった、厳密なルールを設定するケースもあり、コンテンツに対するこだわりを持っていらっしゃいます。
土屋氏:地上波テレビとYouTubeのクロスメディアプランニングは1つのパターンになっていますが、
地上波テレビとYouTubeとでは、コンテンツや視聴体験の同質性がない中で、福原さんが仰っている通り可能な限り安価にリーチを補完するというというものです。
今はTVerも広告在庫が増加してきておりますし、広告主の方にプレミアムなAVOD広告枠の価値を評価頂ける様に努めています。
―放送局がTVCMをプログラマティックでバイイング出来るサービスを開始しましたが、今後TVCMでもプログラマティックバイイングが主流になるのでしょうか?
土屋氏:広告枠が有限、固定的である以上、主流になるとは言えませんが一部の広告枠をデジタル化していくという動きはあると思います。先ほどテレビでターゲティングをするという話がありましたが、欧米ではアドレッサブルと呼ばれる、地上波テレビ広告枠をターゲティング可能にする技術が出来てきています。
本篇の再生は地上波受信によるものですが、インターネット結線されているテレビに対して、広告はインターネット経由で配信されるという物です。
アドレッサブルというのは、まさにこの切り替えをスムーズにして、ターゲティングをすることが出来るという技術です。これについては、徐々にフィージビリティが高まってきておりプログラマティックバイイングを後押しする要因になり得ると思います。
―現状は寡占化されている日本において、媒体社が広告在庫をオープン化して、プログラマティックで買い付けが出来るようにするインセンティブはどこにあるのでしょうか?

土屋氏:広告業界におけるオープン化というのは聞こえは良いのですが、一方でクリエイティブや視聴体験の悪化に繋がる様な印象が媒体としてはあります。我々はオープンであっても事前にクリエイティブの審査をする必要性があると感じています。この作業はAIの進化によって、かなりスピーディーになり事後審査によるベストエフォートな物と事前審査とのタイムラグを中長期的には改善してくれると期待しています。
これまで、オープンな環境で事後考査もしくは事前審査はしていると言っているが明らかにその精度について疑わしい仕組みが広がったことで、劣悪な体験が増えてしまったのでしょう。そういった環境へそのまま我々がでていくことはないでしょう。
一方で、広告枠のデジタル化というのは広告枠の特性が多様化し枠数も爆発的に増えるという事です。そう考えると中小規模でも、業態やクリエイティブの考査、出稿単価に問題がなければ、我々としては出稿頂きたいと当然考えます。広告主としてもプレミアムな媒体に簡単にアクセスできる事は良いことだとお思います。そうなると結果としてオープンでプログラマティックというのは我々の広告枠を埋めてくれて広告主にもその価値を与えてくれる物になると思います。そういった意味では、オープンだクローズドだという事にあまり囚われるのは良くないのではないかと思います。
香川氏:デジタルの世界では、ディスプレイ広告とストリーミング広告では、フォーマットが異なりますが、ディスプレイ広告において、最初は予約型広告のみで、その後プログラマティック化し、プログラマティックが中心になったように、ストリーミング広告もプログラマティックが主流になっていく点には議論の余地はないと思っています。
メリットは、媒体社からすると圧倒的な数の広告主からの出稿を受けられることや、取引の簡便化などが挙げられます。プログラマティック取引は、標準化された自動入札の取引ですので、マニュアル作業は大幅に軽減されます。将来は、より簡略化された最適な取引として発展していく可能性もあります。
―プログラマティックに対する期待する点はありますか?
福原氏:香川さんがおっしゃったように、デジタルの良いところを取り入れて、まずは発展していけるのはとてもいいことかなと思います。
香川氏:意外な話かもしれませんが、テレビCMで当たり前にできていることが、逆にコネクテッドテレビではできていなかった、そんなこともあります。テレビCMでは、1つの番組で複数の広告主が入りますが、同業種の競合企業の広告が並ぶことはありません。例えばトヨタ、ホンダ、スズキのCMが連続して出ることはありませんよね。
コネクテッドテレビでは、当初これが出来なかったのですが、技術が確立してできるようになりました。
具体的には、OpenRTB2.6というプロトコルのお陰です。当社では、OpenRTB2.6をIABTechLabと一緒に作ってきました。このプロトコルに含まれる広告Podという技術により、テレビの視聴者や広告主が当たり前と感じている視聴体験をコネクテッドテレビでも実現することが出来るようになりました。
もう一つ海外で今注目を集めているのが、ライブストリーミングです。ライブストリーミングは、どのタイミングでどのくらいのユーザーが見に来るのかが予測できないものです。
視聴者の注目を集める試合のピーク時に、広告出稿の大チャンスが訪れます。
視聴者数が集中した時の大規模な自動広告取引に耐えうる技術的なインフラの開発に、世界の注目が集まっています。当社は業界標準を構築し、これを現実のものとするために貢献していきます。
土屋氏:ライブスポーツは、一部の伝統的で非常に人気なものを除くとインプレッション数の予測が難しく、純広告として枠を販売していくのが難しかったのです。
これをプログラマティックで販売できるようになると、マネタイズがしやすくなることが期待されます。
また、コネクテッドテレビ画面は大きいので、Lバンドや、サイド・バイ・サイドと呼ばれるような、画面にコンテンツと広告が一緒に流れるようなフォーマットの提供がしやすくなります。例えば、一般的にCMが入れにくいと言われているサッカーの試合でも、ゴールが決まったとき、挿入するなどの取り組みが出来るようになります。
そういった意味でも、コネクテッドテレビとプログラマティックで、ライブスポーツのマネタイズの可能性が広がります。
香川氏:国内でもストリーミング広告のプログラマティック取引は着実に伸びていきます。グローバル市場で事業を手掛ける当社としては、欧米市場のベストプラクティスと技術を提供し、国内市場の発展を支える役割を、引き続き担っていきたいと思います。
ABOUT 野下 智之
ExchangeWire Japan 編集長
慶応義塾大学経済学部卒。
外資系消費財メーカーを経て、2006年に調査・コンサルティング会社シード・プランニングに入社。
国内外のインターネット広告業界をはじめとするデジタル領域の市場・サービスの調査研究を担当し、関連する調査レポートを多数企画・発刊。
2016年4月にデジタル領域を対象とする市場・サービス評価をおこなう調査会社 株式会社デジタルインファクトを設立。
2021年1月に、行政DXをテーマにしたWeb情報媒体「デジタル行政」の立ち上げをリード。